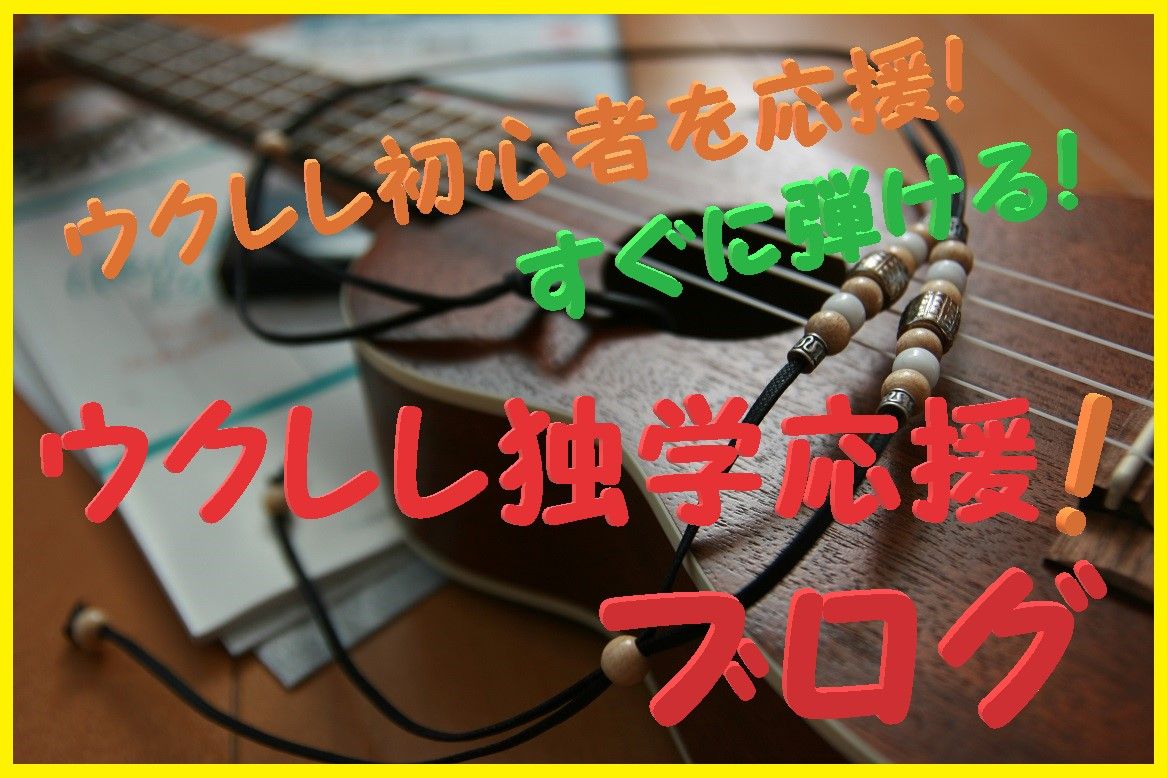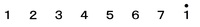2018年05月24日
『固定ド』と『移動ド』の違いについて~日本のピアノ学習の失敗~
⇒【sinyaが開発!弾く脳トレ!よなおしギター】
一連の二胡関連記事で、私は『固定ド』『移動ド』という言葉を多用しています。
分かりやすくするために便宜上これらの言葉を使っているのですが、これらの言葉、特に『固定ド』という言葉は何か違和感があるんですね。
厳密に言えば、『固定されるド』というものは存在しません。
しかし日本では、『固定ド』『移動ド』という言葉が当たり前に使われています。
違和感のある言葉、本来は存在しない言葉が使われるのには、日本の音楽教育、主にピアノ学習における失敗が関係しているからかもしれません。
二胡の練習方法の記事を書く前に、まずはこの『固定ド』と『移動ド』の違いについて明確にしていきましょう。
※記事内では長調についてのみ解説しています。
『音名』『階名』という言葉があります。
似ているようで全く意味の異なるこの2つの言葉には、それぞれで表記の仕方にお約束があります(日本の場合)。
☆『音名』の表記の仕方
ハ・ニ・ホ・ヘ・ト・イ・ロ
または
C・D・E・F・G・A・B
☆『階名』の表記の仕方
ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ
一般的には、『音名』は絶対的な音を表し『階名』は相対的な音を表すときに使うと説明されます。
日本では、この『音名』と『階名』の違いがあやふやになっている人が多いんですね。私も含めてですが......
ピアノ経験者である妻が二胡の『移動ド』方式の練習で混乱してしまう要因も、この日本人の『音名』と『階名』の認識の曖昧さにあるのではないかと思い私なりにイロイロ考えてみることにしました。
『音名』と『階名』の表記法を見ると、音楽の授業やピアノのレッスンで音を表すのは『階名(ドレミ)』だということが分かります。
つまり、ピアノでの、いわゆる『固定ド』方式のレッスンでは『全ての音を階名(ドレミ)だけで表現する』と言っても良いかもしれません。
でもその考え方は間違っていると言えます。
そう書くと、『音をドレミで表すのは当たり前でしょ!』と思うかもしれませんが、実際には階名(ドレミ)だけでは特定の1音を表現することは出来ません。
さぁ、得意の擬人化で説明してみましょう!
ここに、『Aさん』『Bさん』『Cさん』という家族があるとします。その3家族にはそれぞれ3人の息子がいるとします。
そして、その子供たちの名前が『一郎』『次郎』『三郎』と全ての家族で同じだったとします。
そうなると、3家族で9人いる男の子の内の1人を特定するとき、ただ『次郎くん』と言っても誰だか分かりません。もし特定の1人を指し示すのなら『Aさんちの次郎くん』のように言わなければなりませんよね。
それと同じことが『音名』と『階名』にも言えます。
家で例えるなら『音名は苗字』『階名は名前』を表すのに使います。
つまり、特定の1音を表すのに階名(ドレミ)だけでは不十分ということになります。
曲の調(Key)を表すときって、『イロハ』か『ABC』を使いますよね。つまり『音名』です。
例えば、ハ長調とかイ短調、あるいは KeyC とか KeyAm のように表記します。
決して『階名』で『ド長調』や『Keyラ』とは表記しないんです。
調(キイ)とは、例えば KeyC の曲の場合『この曲はCグループのドレミが使われます!』という宣言みたいなものなんです。
家族でいうなら、「今日はCさんちの一郎くん次郎くん三郎くんに歌ってもらいましょう!」みたいな感じです。
ですから、『階名』で『ド長調』と表記してしまうと「今日は一郎くんちの一郎くん次郎くん三郎くんに歌ってもらいましょう!」と言ってるのと同じで、どこの家の兄弟が歌うのか分からなくなっちゃうんですね。
つまり、ある1音を特定したいのなら、例えば『ハ長調のド』とか『KeyDのシ』とか『G調のファ』という言い方をしないとダメだということです。
『音名』による調の特定と『階名』による順番の特定によりようやく1つの音が意味のある音として特定できるわけです。
ここで疑問が浮かびます。
ピアノ経験がある人、あるいは、楽器の経験が無くても学校の音楽の授業を真面目に受けていた人は、「ピアノでドを弾いてください!」と言われれば、何の躊躇(ちゅうちょ)もなく下の画像の赤点を弾くでしょう。

これは、『ド』という階名だけで1音を特定できたことになります。
「一郎くんを連れて来て」と言われただけですぐにどこの家の一郎くんか分かっちゃう感じです。
これまで、『階名(ドレミ)』だけでは1音を特定できない、1音を特定したいなら『ハ長調のド』のように言わないとダメと書いてきましたが、それは嘘なのかってなりますよね。
なんでピアノ経験者、あるいは私も含め鍵盤の並びが分かる人は、「ド」と言われただけで1音を特定できるのでしょうか?
このブログで私はたびたび『ピアノはハ長調(KeyC)の楽器』ということを書いています。同時に、五線譜もハ長調のツールだということも。
ピアノはハ長調(KeyC)の曲を弾く時がもっとも分かりやすいよう出来ています。
これは、ピアノの鍵盤を見ていただければ一目瞭然です。
白く塗られ前面に出て目立つ白鍵は、全てハ長調で使われる音です。逆に、ハ長調では使わない鍵盤は、目立たない黒色に塗られ後ろに追いやられています。
これってつまり、C家の家長が「一郎次郎三郎はC家の子供達しか認めない。ウチの子を主役にする!」と、自分の家の子供だけ超絶えこひいきしている状態なんですね。
ピアノはCさんちの家そのものと言えます。そしてこのモンスターペアレントのような超絶えこひいきは、今の日本で広く受け入れられています。
これが日本の『固定ド』の考え方です。
例えば、ハ長調、ニ長調、ト長調では始まりの音はもちろん違う音です。でもそれら始まりの音は全て『ド』という階名による共通の名前が付き、その後は『レミファソラシ』と続いていきます。
それを強引に『ドは KeyC の始めの音しか認めない』つまり『ドをハ長調の始めの音に固定する』とやったわけです。
この超絶えこひいきの価値観が、いま日本にまんえいしているんですね。
そして、ピアノを習う人も、学校で音楽の授業を受ける子供たちも、そうとは知らずその価値観の中で音楽を学んでいます。
つまり、日本で音楽を学ぶ人の多くが知らずにC一族の末裔(まつえい)になっているんです。
その証拠に、「一郎を呼んできて」と言われれば何の疑いもなくC家の一郎くんを連れて来てしまうように……
「ドを弾いてみて」と言われれば、何の疑いもなく『ハ長調のド』を弾いてしまうんですね。
日本人の多くがC一族の末裔だとしても、音楽に携わらない人、あるいは趣味でピアノを弾く程度なら全く支障はありません。
現に、中学までピアノを習っていた妻は、C一族の中でもかなりその価値観を刷り込まれた人間となりますが、これまで何の支障もありませんでした。
二胡を習うまでは....
妻は二胡に取り組むようになり『移動ド』という概念を初めて知ることで
「え~!!!一郎って他の家にもいたの?」
と、驚愕し混乱したわけですね。
そして、そこで初めて気付くのです。
『一郎はC家にしかいない』と嘘を教えられていたこと、つまり『ドはハ長調の始まりの音にしか存在しない』という嘘を教えられていたことに。
二胡は『移動ド』という概念で練習します。
ただ、この『移動ド』という概念はそもそも当たり前のことなので、わざわざ『移動ド』という言い方をしなければならないのは、やはり日本がC一族に支配されているからなんですね。
『移動ド』とは、「C家に限らずどの家でも始めに生まれた子は一郎くんと名前が付くんですよ!」ということ。
つまり、「ハ長調に限らずどの調(Key)でも最初の音はドと名前が付くんですよ」ということなんです。
どの家もえこひいきせず、「みんな平等ですよ」という当たり前で常識的な考え方です。
ですから、二胡のレッスンでの「D調のドレミを弾きましょう!」「G調のドレミを弾きましょう!」という言い方はなんら問題が無く、逆にその言葉で混乱する方が本来はおかしいんですね。
特に幼いころからピアノを習っている、例えばウチの妻のような人は、耳も相当にC一族に鍛えられています。
その為、『D調のドはレにしか聞こえない』『G調のドはソにしか聞こえない』という状態になります。
全てハ長調の中の音でしか捉えられないんです。
だから、二胡での『移動ド』方式の練習で混乱するわけですね。
そろそろ日本はC一族からの呪縛を解く必要があるように思います。その方法は、決して難しくありません。
某大手音楽教室『ヤ〇ハ音楽教室』。日本のピアノ学習に与える影響がかなり大きいと思われるその教室のテレビCMをご覧になったことがある方は多いと思います。
その中で子供たちは先生の伴奏に合わせこう歌います...
「ドレミファ ソーラファ ミ・レ・ド~」
ウチの息子も通っていましたので、この曲をたくさん歌いました。ただ、その時の伴奏はハ長調、つまりKeyCでの伴奏だけだったんですね。
これを、イロイロな調の伴奏で子供たちに歌ってもらえばよいんです。もちろん何の調であっても歌詞は同じ....
「ドレミファ ソーラファ ミ・レ・ド~」
このような歌い方を『移動ド唱法』といいますね。楽しみながら自然と『ドレミで歌えるのはハ長調だけじゃない』ということが身に付く方法です。
また、少し年齢が進めばこんなこともできるかもしれません。
先生が1つ和音を弾きます。KeyDだったらDコードを『ジャ~ン』と。そして先生が「この響きに合ったドを弾いてください!」と問題を出し子供たちに鍵盤で弾いてもらう。
子供はこれで、曲の中でスケールの何番目の音(ここでは1番目の『ド』)がどういう役割になるかということが分かるようになります。よい演奏をする上で非常に大切な音の捉え方です。
いずれにしても、ポイントは2つ。
1、幼いころから『移動ド』を当たり前にする
2、必ず『音名(調)』と『階名』のセットで音を認識させる
妻が二胡の『移動ド』方式の練習で苦戦している姿を見ると、C一族の価値観の刷り込みは相当に根深いなと感じます。
子供たちがずっと音楽や楽器を楽しんでいけるように、C一族の呪縛は早いうちに解いた方が良いと思うわけです。
☆二胡を弾いてみた!二胡関連記事
・二胡を練習して分かったこと~度数で音楽理論を学ぶことの利点~
・二胡の新しい練習方法を考えてみる~ピアノ経験者向け~
・『固定ド』と『移動ド』の違いについて~日本のピアノ学習の失敗~
・「押さえる場所が分からない!」を解決~二胡の効率的な練習方法を考える1~
・二胡の練習用ツール『二胡棒』を作ろう!~二胡の効率的な練習方法2
・二胡棒の驚くべき効果!~音程が合わない!を解決する方法~
【『移動ド』と『移動ド唱法』についてはこの本でマスター!】
・音感が身に付く本!~童謡を聞くだけで音感が身につくCDブック~
【スケールの何番目の音が曲の中でどんな役割を持つのか?】
・メジャースケールの各音の特徴~優等生とヤンチャ坊主~


【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!
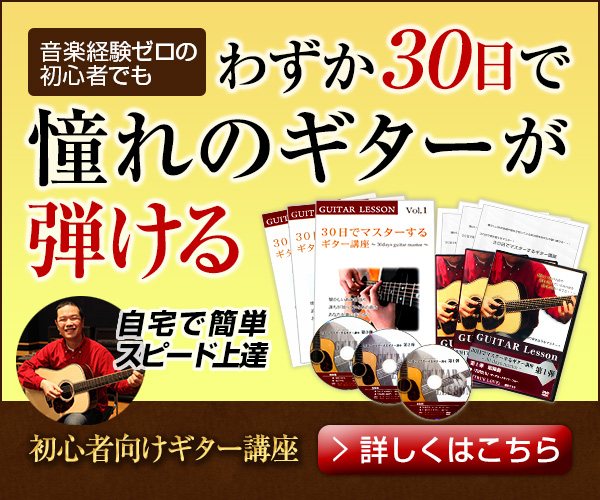

一連の二胡関連記事で、私は『固定ド』『移動ド』という言葉を多用しています。
分かりやすくするために便宜上これらの言葉を使っているのですが、これらの言葉、特に『固定ド』という言葉は何か違和感があるんですね。
厳密に言えば、『固定されるド』というものは存在しません。
しかし日本では、『固定ド』『移動ド』という言葉が当たり前に使われています。
違和感のある言葉、本来は存在しない言葉が使われるのには、日本の音楽教育、主にピアノ学習における失敗が関係しているからかもしれません。
二胡の練習方法の記事を書く前に、まずはこの『固定ド』と『移動ド』の違いについて明確にしていきましょう。
※記事内では長調についてのみ解説しています。
【次郎ってどこの家の子?】
『音名』『階名』という言葉があります。
似ているようで全く意味の異なるこの2つの言葉には、それぞれで表記の仕方にお約束があります(日本の場合)。
☆『音名』の表記の仕方
ハ・ニ・ホ・ヘ・ト・イ・ロ
または
C・D・E・F・G・A・B
☆『階名』の表記の仕方
ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ
一般的には、『音名』は絶対的な音を表し『階名』は相対的な音を表すときに使うと説明されます。
日本では、この『音名』と『階名』の違いがあやふやになっている人が多いんですね。私も含めてですが......
ピアノ経験者である妻が二胡の『移動ド』方式の練習で混乱してしまう要因も、この日本人の『音名』と『階名』の認識の曖昧さにあるのではないかと思い私なりにイロイロ考えてみることにしました。
『音名』と『階名』の表記法を見ると、音楽の授業やピアノのレッスンで音を表すのは『階名(ドレミ)』だということが分かります。
つまり、ピアノでの、いわゆる『固定ド』方式のレッスンでは『全ての音を階名(ドレミ)だけで表現する』と言っても良いかもしれません。
でもその考え方は間違っていると言えます。
そう書くと、『音をドレミで表すのは当たり前でしょ!』と思うかもしれませんが、実際には階名(ドレミ)だけでは特定の1音を表現することは出来ません。
さぁ、得意の擬人化で説明してみましょう!
ここに、『Aさん』『Bさん』『Cさん』という家族があるとします。その3家族にはそれぞれ3人の息子がいるとします。
そして、その子供たちの名前が『一郎』『次郎』『三郎』と全ての家族で同じだったとします。
そうなると、3家族で9人いる男の子の内の1人を特定するとき、ただ『次郎くん』と言っても誰だか分かりません。もし特定の1人を指し示すのなら『Aさんちの次郎くん』のように言わなければなりませんよね。
それと同じことが『音名』と『階名』にも言えます。
家で例えるなら『音名は苗字』『階名は名前』を表すのに使います。
つまり、特定の1音を表すのに階名(ドレミ)だけでは不十分ということになります。
【どうやって1音を特定するのか?】
曲の調(Key)を表すときって、『イロハ』か『ABC』を使いますよね。つまり『音名』です。
例えば、ハ長調とかイ短調、あるいは KeyC とか KeyAm のように表記します。
決して『階名』で『ド長調』や『Keyラ』とは表記しないんです。
調(キイ)とは、例えば KeyC の曲の場合『この曲はCグループのドレミが使われます!』という宣言みたいなものなんです。
家族でいうなら、「今日はCさんちの一郎くん次郎くん三郎くんに歌ってもらいましょう!」みたいな感じです。
ですから、『階名』で『ド長調』と表記してしまうと「今日は一郎くんちの一郎くん次郎くん三郎くんに歌ってもらいましょう!」と言ってるのと同じで、どこの家の兄弟が歌うのか分からなくなっちゃうんですね。
つまり、ある1音を特定したいのなら、例えば『ハ長調のド』とか『KeyDのシ』とか『G調のファ』という言い方をしないとダメだということです。
『音名』による調の特定と『階名』による順番の特定によりようやく1つの音が意味のある音として特定できるわけです。
ここで疑問が浮かびます。
ピアノ経験がある人、あるいは、楽器の経験が無くても学校の音楽の授業を真面目に受けていた人は、「ピアノでドを弾いてください!」と言われれば、何の躊躇(ちゅうちょ)もなく下の画像の赤点を弾くでしょう。

これは、『ド』という階名だけで1音を特定できたことになります。
「一郎くんを連れて来て」と言われただけですぐにどこの家の一郎くんか分かっちゃう感じです。
これまで、『階名(ドレミ)』だけでは1音を特定できない、1音を特定したいなら『ハ長調のド』のように言わないとダメと書いてきましたが、それは嘘なのかってなりますよね。
なんでピアノ経験者、あるいは私も含め鍵盤の並びが分かる人は、「ド」と言われただけで1音を特定できるのでしょうか?
【みんなC一族の末裔】
このブログで私はたびたび『ピアノはハ長調(KeyC)の楽器』ということを書いています。同時に、五線譜もハ長調のツールだということも。
ピアノはハ長調(KeyC)の曲を弾く時がもっとも分かりやすいよう出来ています。
これは、ピアノの鍵盤を見ていただければ一目瞭然です。
白く塗られ前面に出て目立つ白鍵は、全てハ長調で使われる音です。逆に、ハ長調では使わない鍵盤は、目立たない黒色に塗られ後ろに追いやられています。
これってつまり、C家の家長が「一郎次郎三郎はC家の子供達しか認めない。ウチの子を主役にする!」と、自分の家の子供だけ超絶えこひいきしている状態なんですね。
ピアノはCさんちの家そのものと言えます。そしてこのモンスターペアレントのような超絶えこひいきは、今の日本で広く受け入れられています。
これが日本の『固定ド』の考え方です。
例えば、ハ長調、ニ長調、ト長調では始まりの音はもちろん違う音です。でもそれら始まりの音は全て『ド』という階名による共通の名前が付き、その後は『レミファソラシ』と続いていきます。
それを強引に『ドは KeyC の始めの音しか認めない』つまり『ドをハ長調の始めの音に固定する』とやったわけです。
この超絶えこひいきの価値観が、いま日本にまんえいしているんですね。
そして、ピアノを習う人も、学校で音楽の授業を受ける子供たちも、そうとは知らずその価値観の中で音楽を学んでいます。
つまり、日本で音楽を学ぶ人の多くが知らずにC一族の末裔(まつえい)になっているんです。
その証拠に、「一郎を呼んできて」と言われれば何の疑いもなくC家の一郎くんを連れて来てしまうように……
「ドを弾いてみて」と言われれば、何の疑いもなく『ハ長調のド』を弾いてしまうんですね。
【C一族による洗脳が解けた瞬間】
日本人の多くがC一族の末裔だとしても、音楽に携わらない人、あるいは趣味でピアノを弾く程度なら全く支障はありません。
現に、中学までピアノを習っていた妻は、C一族の中でもかなりその価値観を刷り込まれた人間となりますが、これまで何の支障もありませんでした。
二胡を習うまでは....
妻は二胡に取り組むようになり『移動ド』という概念を初めて知ることで
「え~!!!一郎って他の家にもいたの?」
と、驚愕し混乱したわけですね。
そして、そこで初めて気付くのです。
『一郎はC家にしかいない』と嘘を教えられていたこと、つまり『ドはハ長調の始まりの音にしか存在しない』という嘘を教えられていたことに。
【えこひいきしない常識的な『移動ド』】
二胡は『移動ド』という概念で練習します。
ただ、この『移動ド』という概念はそもそも当たり前のことなので、わざわざ『移動ド』という言い方をしなければならないのは、やはり日本がC一族に支配されているからなんですね。
『移動ド』とは、「C家に限らずどの家でも始めに生まれた子は一郎くんと名前が付くんですよ!」ということ。
つまり、「ハ長調に限らずどの調(Key)でも最初の音はドと名前が付くんですよ」ということなんです。
どの家もえこひいきせず、「みんな平等ですよ」という当たり前で常識的な考え方です。
ですから、二胡のレッスンでの「D調のドレミを弾きましょう!」「G調のドレミを弾きましょう!」という言い方はなんら問題が無く、逆にその言葉で混乱する方が本来はおかしいんですね。
特に幼いころからピアノを習っている、例えばウチの妻のような人は、耳も相当にC一族に鍛えられています。
その為、『D調のドはレにしか聞こえない』『G調のドはソにしか聞こえない』という状態になります。
全てハ長調の中の音でしか捉えられないんです。
だから、二胡での『移動ド』方式の練習で混乱するわけですね。
【C一族の呪縛を解く方法】
そろそろ日本はC一族からの呪縛を解く必要があるように思います。その方法は、決して難しくありません。
某大手音楽教室『ヤ〇ハ音楽教室』。日本のピアノ学習に与える影響がかなり大きいと思われるその教室のテレビCMをご覧になったことがある方は多いと思います。
その中で子供たちは先生の伴奏に合わせこう歌います...
「ドレミファ ソーラファ ミ・レ・ド~」
ウチの息子も通っていましたので、この曲をたくさん歌いました。ただ、その時の伴奏はハ長調、つまりKeyCでの伴奏だけだったんですね。
これを、イロイロな調の伴奏で子供たちに歌ってもらえばよいんです。もちろん何の調であっても歌詞は同じ....
「ドレミファ ソーラファ ミ・レ・ド~」
このような歌い方を『移動ド唱法』といいますね。楽しみながら自然と『ドレミで歌えるのはハ長調だけじゃない』ということが身に付く方法です。
また、少し年齢が進めばこんなこともできるかもしれません。
先生が1つ和音を弾きます。KeyDだったらDコードを『ジャ~ン』と。そして先生が「この響きに合ったドを弾いてください!」と問題を出し子供たちに鍵盤で弾いてもらう。
子供はこれで、曲の中でスケールの何番目の音(ここでは1番目の『ド』)がどういう役割になるかということが分かるようになります。よい演奏をする上で非常に大切な音の捉え方です。
いずれにしても、ポイントは2つ。
1、幼いころから『移動ド』を当たり前にする
2、必ず『音名(調)』と『階名』のセットで音を認識させる
妻が二胡の『移動ド』方式の練習で苦戦している姿を見ると、C一族の価値観の刷り込みは相当に根深いなと感じます。
子供たちがずっと音楽や楽器を楽しんでいけるように、C一族の呪縛は早いうちに解いた方が良いと思うわけです。
☆二胡を弾いてみた!二胡関連記事
・二胡を練習して分かったこと~度数で音楽理論を学ぶことの利点~
・二胡の新しい練習方法を考えてみる~ピアノ経験者向け~
・『固定ド』と『移動ド』の違いについて~日本のピアノ学習の失敗~
・「押さえる場所が分からない!」を解決~二胡の効率的な練習方法を考える1~
・二胡の練習用ツール『二胡棒』を作ろう!~二胡の効率的な練習方法2
・二胡棒の驚くべき効果!~音程が合わない!を解決する方法~
【『移動ド』と『移動ド唱法』についてはこの本でマスター!】
・音感が身に付く本!~童謡を聞くだけで音感が身につくCDブック~
【スケールの何番目の音が曲の中でどんな役割を持つのか?】
・メジャースケールの各音の特徴~優等生とヤンチャ坊主~


【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!
Posted by sinya at 22:38
│音楽理論