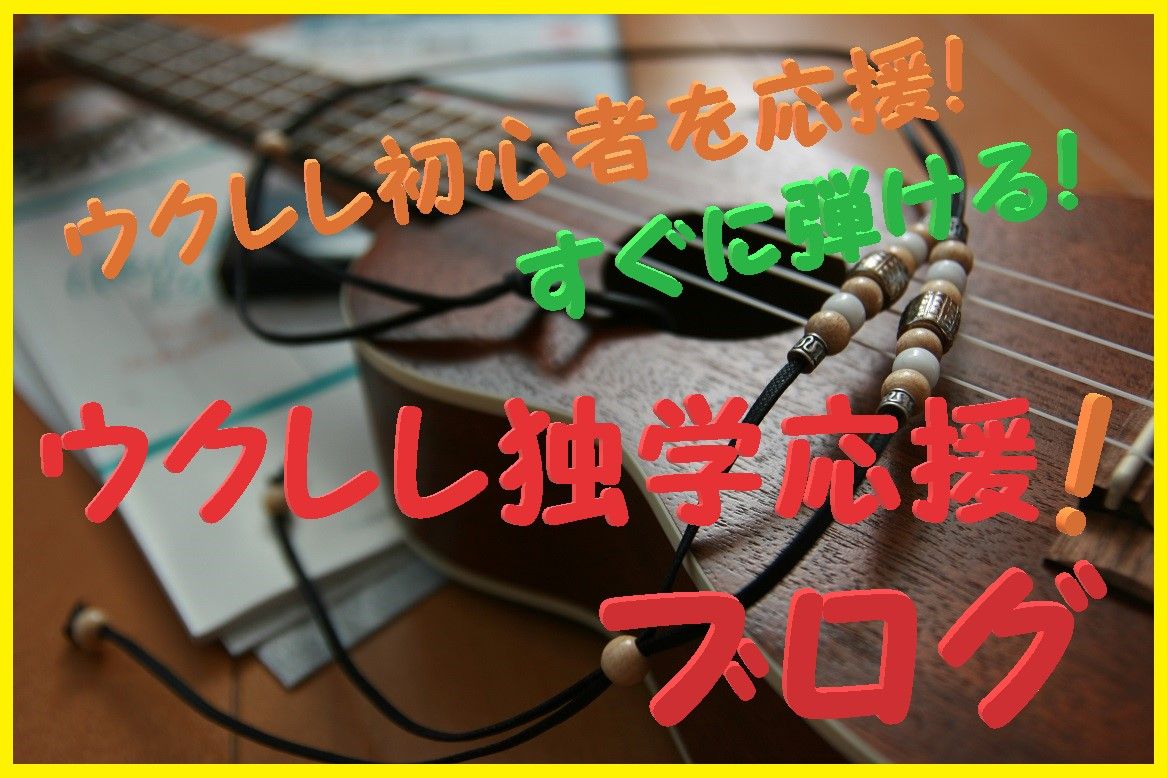2013年04月30日
ギター専用楽譜度数譜のコード表記
⇒【sinyaが開発!弾く脳トレ!よなおしギター】
以前、記事にて・ギター専用楽譜『度数譜』 補足の説明をした時に『コード表記の仕方も確立しています』と書きました。
その後、そのコード表記の仕方を記事にしようと思っていたのですが、スッカリ忘れていました。
なので本日は、『度数譜によるコード表記の仕方』をご説明します。
といっても、全く難しくありませんので、少しでも興味のある方はちょっと読んでいって下さい。
取りあえず、いくつかのコードを度数譜に表してみたのでご覧下さい。

度数譜ですので、数字は当然『度数』になります。
中央の線より上の数字は、1~3弦にある音を表します。
中央の線より下の数字は、4~6弦にある音を表します。

『×』マークは、その弦の音は出しません。いわゆるミュートです。

ご覧のように、この表記の仕方だと、まず最も大切な『ルート(1度)』が何弦にあるのかが一目瞭然ですね。
続いて、3度や7度が『メジャー』なのか『マイナー(♭)』なのかも直ぐに分かります。
そして、曲者のテンションノートも、どの弦に何の音があるのか見れば直ぐに分かります。
さらに、度数譜の『キイが変わっても書き換えの必要が無い』という最大の特徴は、もちろんこのコード表記にも適用されます。
例えば、上のコード表のルート音をCからDに変えてみると、以下のようになります。

コードネームが変わっただけで、度数譜は一切変わっていませんね。
※開放弦を使ったコードに関しては、ルート音によって押さえ方が変わりますので、その点は注意です。
今までのコードブックなどは、全てのルート音に対して、全てのコードタイプを掲載してあったりして、とても容量が多くなってしまう傾向にありましたが。もし、度数譜によるコード表記でコードブックを作れば、もっとシンプルなものが出来上がるでしょう。
そして、このコード表記の最大の利点が『自分が押さえて奏でている音が何度の音なのかが分かる』ことです。
『ルートに対してこの度数の音を押さえているから、このコードはこんな響きになるんだ』ということが、耳で聞いて分かるのはもちろん、視覚的にも理解できる訳で。これは、コードというものを理解し、ひいては、コードを自分で考えて作っていく事に直結します。
コードの構造とその響きを理解し、自分から奏でたい響き(コード)を作っていくことが出来れば、ギターを意のままに操ることが出来ることになりますね。
そういった意味では、この『度数譜によるコード表記』を利用してギターの演奏をすることは、非常に有意義なことだと思うのですが・・・
ただ、このコード表記にも欠点があります。
まず、メロディの度数譜と同じで、『ギターの指板上の度数配列が分からないと弾けない』ことです。
まぁ、もともと度数譜が、『ギターの指板上の度数配列を覚える為のツール』として生まれたのですから、当然といえば当然なんですが。
やはり、TAB譜やコードの押さえ方が図で分かるようなコード表記の仕方に比べれば、どうしても押さえるのに時間が掛かるかもしれません。
逆に、この度数譜によるコード表記で、直ぐにコードを押さえることが出来る人は、もうギターを意のままに操ることが可能になってくるでしょう。
度数譜によるメロディの表記と同じように、このコード表記に関しても、やはり『練習用ツール』としての役割が大きいかもしれません。
もう一つの欠点は、知名度です。
インターネットで、ギターリストの方や教室の講師の方の書いた記事などを読むと、『度数の大切さ』を、とても真剣に伝えようとしている方が多いのが分かります。
ある程度ギターを弾ける方もそうですが、初心者の方は特に、この『度数』を意識して練習することにより飛躍的にギターの技術が向上すると思います。『度数の大切さ』を分かっている方は、そのことを知っていますので、どうにか、ギターを習得しようとする人達にもその『大切さ』を分かって欲しいと思っているはずです。もちろん私もその一人です。
ただ、やはり、全世界的に見て、音楽の共通言語は『五線譜』ですよね。
これはもう、絶対に変えようが無いものです。
ですから、楽器を演奏する以上、五線譜とは一生縁が切れないんです。それが、ギターという楽器と非常に相性が悪いものであってもです。
さらに、ギターの世界では、TAB譜が当たり前になり過ぎてしまいましたね。TAB譜が悪い訳ではないのですが、簡単だからといって、TAB譜だけで練習していては、一生続けてもギターの構造を理解することは出来ないでしょう。
『五線譜とTAB譜の普及』が、いくら『ギターリストには度数が大切です!』と伝えようとしても、その真意が伝わり難い要因であるのは確かだと思うんです。
その証拠に、度数譜のように『度数だけで表された楽譜』を、私は一度だって見たことが無いのですから。
『度数』自体の知名度が低ければ当然、『度数譜』も『度数譜によるコード表記』も、知名度が上がるはずも無く。それらが、日の目を見ないままでいるのは仕方無いんです。
ですから、『度数』の大切さを知っている私も、教室では当たり前のように、五線譜で理論のレッスンをしますし、TAB譜の読み方も教えています。
そうせざるを得ない、と言ったところでしょうか。
これからギターを習得しようとする人達のために、練習用としてで良いので、『度数のみで表記された楽譜』が、楽器屋さんの店頭に並ぶ時代が来れば良いな~と、私は本気で思っています。
☆度数譜関連記事
・ギター専用楽譜『度数譜』
・ギター専用楽譜『度数譜』 補足
・ある曲の度数譜 答え
・ギター専用楽譜度数譜による『大きな古時計』
・ギター専用楽譜度数譜による『さんぽ』
・ギター専用楽譜度数譜による『Hey Jude』
・ギター専用楽譜度数譜のコード表記


【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!
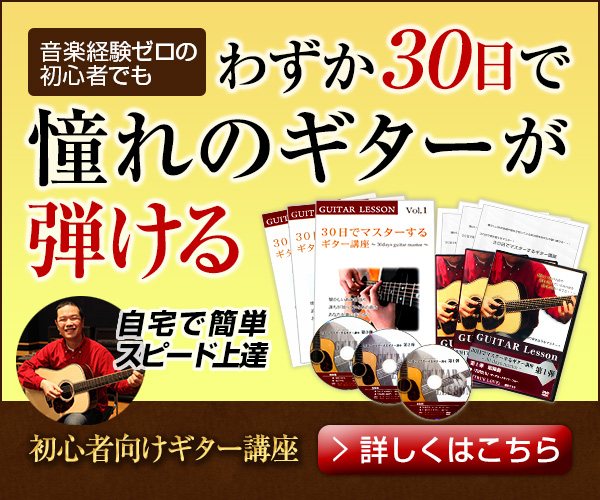

以前、記事にて・ギター専用楽譜『度数譜』 補足の説明をした時に『コード表記の仕方も確立しています』と書きました。
その後、そのコード表記の仕方を記事にしようと思っていたのですが、スッカリ忘れていました。
なので本日は、『度数譜によるコード表記の仕方』をご説明します。
といっても、全く難しくありませんので、少しでも興味のある方はちょっと読んでいって下さい。
取りあえず、いくつかのコードを度数譜に表してみたのでご覧下さい。
度数譜ですので、数字は当然『度数』になります。
中央の線より上の数字は、1~3弦にある音を表します。
中央の線より下の数字は、4~6弦にある音を表します。
『×』マークは、その弦の音は出しません。いわゆるミュートです。
ご覧のように、この表記の仕方だと、まず最も大切な『ルート(1度)』が何弦にあるのかが一目瞭然ですね。
続いて、3度や7度が『メジャー』なのか『マイナー(♭)』なのかも直ぐに分かります。
そして、曲者のテンションノートも、どの弦に何の音があるのか見れば直ぐに分かります。
さらに、度数譜の『キイが変わっても書き換えの必要が無い』という最大の特徴は、もちろんこのコード表記にも適用されます。
例えば、上のコード表のルート音をCからDに変えてみると、以下のようになります。
コードネームが変わっただけで、度数譜は一切変わっていませんね。
※開放弦を使ったコードに関しては、ルート音によって押さえ方が変わりますので、その点は注意です。
今までのコードブックなどは、全てのルート音に対して、全てのコードタイプを掲載してあったりして、とても容量が多くなってしまう傾向にありましたが。もし、度数譜によるコード表記でコードブックを作れば、もっとシンプルなものが出来上がるでしょう。
そして、このコード表記の最大の利点が『自分が押さえて奏でている音が何度の音なのかが分かる』ことです。
『ルートに対してこの度数の音を押さえているから、このコードはこんな響きになるんだ』ということが、耳で聞いて分かるのはもちろん、視覚的にも理解できる訳で。これは、コードというものを理解し、ひいては、コードを自分で考えて作っていく事に直結します。
コードの構造とその響きを理解し、自分から奏でたい響き(コード)を作っていくことが出来れば、ギターを意のままに操ることが出来ることになりますね。
そういった意味では、この『度数譜によるコード表記』を利用してギターの演奏をすることは、非常に有意義なことだと思うのですが・・・
ただ、このコード表記にも欠点があります。
まず、メロディの度数譜と同じで、『ギターの指板上の度数配列が分からないと弾けない』ことです。
まぁ、もともと度数譜が、『ギターの指板上の度数配列を覚える為のツール』として生まれたのですから、当然といえば当然なんですが。
やはり、TAB譜やコードの押さえ方が図で分かるようなコード表記の仕方に比べれば、どうしても押さえるのに時間が掛かるかもしれません。
逆に、この度数譜によるコード表記で、直ぐにコードを押さえることが出来る人は、もうギターを意のままに操ることが可能になってくるでしょう。
度数譜によるメロディの表記と同じように、このコード表記に関しても、やはり『練習用ツール』としての役割が大きいかもしれません。
もう一つの欠点は、知名度です。
インターネットで、ギターリストの方や教室の講師の方の書いた記事などを読むと、『度数の大切さ』を、とても真剣に伝えようとしている方が多いのが分かります。
ある程度ギターを弾ける方もそうですが、初心者の方は特に、この『度数』を意識して練習することにより飛躍的にギターの技術が向上すると思います。『度数の大切さ』を分かっている方は、そのことを知っていますので、どうにか、ギターを習得しようとする人達にもその『大切さ』を分かって欲しいと思っているはずです。もちろん私もその一人です。
ただ、やはり、全世界的に見て、音楽の共通言語は『五線譜』ですよね。
これはもう、絶対に変えようが無いものです。
ですから、楽器を演奏する以上、五線譜とは一生縁が切れないんです。それが、ギターという楽器と非常に相性が悪いものであってもです。
さらに、ギターの世界では、TAB譜が当たり前になり過ぎてしまいましたね。TAB譜が悪い訳ではないのですが、簡単だからといって、TAB譜だけで練習していては、一生続けてもギターの構造を理解することは出来ないでしょう。
『五線譜とTAB譜の普及』が、いくら『ギターリストには度数が大切です!』と伝えようとしても、その真意が伝わり難い要因であるのは確かだと思うんです。
その証拠に、度数譜のように『度数だけで表された楽譜』を、私は一度だって見たことが無いのですから。
『度数』自体の知名度が低ければ当然、『度数譜』も『度数譜によるコード表記』も、知名度が上がるはずも無く。それらが、日の目を見ないままでいるのは仕方無いんです。
ですから、『度数』の大切さを知っている私も、教室では当たり前のように、五線譜で理論のレッスンをしますし、TAB譜の読み方も教えています。
そうせざるを得ない、と言ったところでしょうか。
これからギターを習得しようとする人達のために、練習用としてで良いので、『度数のみで表記された楽譜』が、楽器屋さんの店頭に並ぶ時代が来れば良いな~と、私は本気で思っています。
☆度数譜関連記事
・ギター専用楽譜『度数譜』
・ギター専用楽譜『度数譜』 補足
・ある曲の度数譜 答え
・ギター専用楽譜度数譜による『大きな古時計』
・ギター専用楽譜度数譜による『さんぽ』
・ギター専用楽譜度数譜による『Hey Jude』
・ギター専用楽譜度数譜のコード表記


【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!
Posted by sinya at 22:37
│度数譜