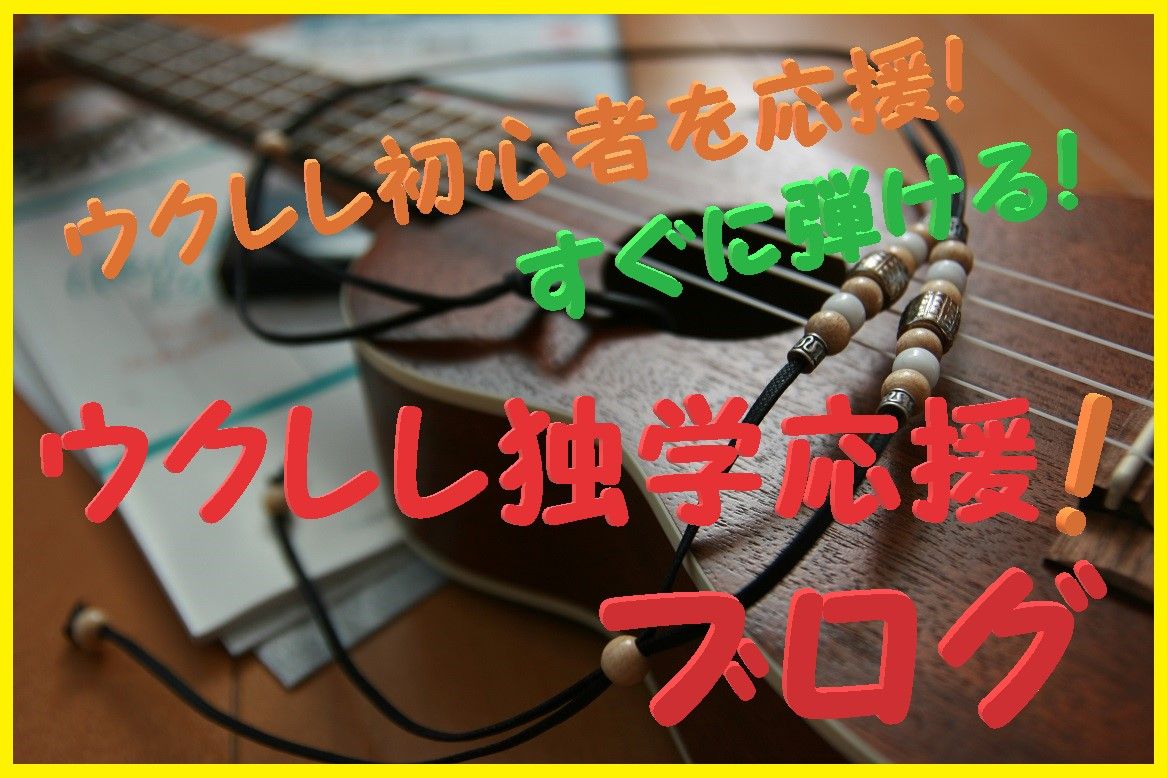2013年02月03日
ヤマハ エレアコギター APX700II の弦高調整 2
⇒【sinyaが開発!弾く脳トレ!よなおしギター】
APX700から外したサドルの底面が、斜めだった件。写真では分かり難かったので、図で説明します。

従来のサドルは、底面が平らです。なので、底面を削る時には、サドルをサンドペーパーに『直角』に当てます。削っている最中にも、時々その『直角』を確認することによって、底面が平らに削られているかどうかの判断をする訳です。
ところが、APX700は図の右のように、サドルの底面が斜めになっていました。これでは、サンドペーパーに『直角』に当てることは出来ません。『直角』に当てることが出来ないということは、平らに削られているかどうかの判断材料を失ってしまうことになります。
とはいえ、いてもたっていられずに始めた作業なので、ここで止めるのも悔しいし、今から新しいサドルを注文して届くまで待てる自信もありません。
で、考えられる案は2つ。
第一案・・・斜めになっている部分を削って平らにしてしまう。
第二案・・・斜めのまま削る。

APX700のサドルの底面が、なぜ斜めになっているのか?その理由は分かりません。ただ、もちろん意味があってのことだと思います。なので、出来れば斜めの状態を保ちたい。
そして、第一案のように斜めの部分をカットしてしまうと、予定の削る量を大幅にオーバーしてしまいます。サドルの底を削る量は、前回の計算では<0.4mm>です。斜めの部分をカットしたら、恐らくその倍は削れてしまいます。
そんなに削ったら、弦高が低くなり過ぎて、音に支障が出てしまうと思います。
という訳で、第二案を決行いたします。
『直角』があてにならない以上、削る前の斜めの角度を保ちながら削る他ありません。
しかし、斜めの角度を正確に保ちながら底面を削る方法が思い浮かばないので、全てを『自分の手の感覚』にゆだねることにしました。
う~ん、職人さんみたいでカッコイイです。もう一度言います、私、アコギの弦高調整は初めてです。
そうと決まりましたので。作業を続行いたします。
前回、手順③までいきましたので、手順④ 削る前のサドルを測定します。
サドルは、真っ白い部品です。そのままでは、どこを基点に測定して良いのか分かりません。なので、計測の基点となる線をマジックで入れます。これは、1弦と6弦の当たる位置の2箇所で良いと思います。が、何となく1弦~6弦の全6箇所に印を付けてしまいました。

この計測基点を元に測ります。

測定の結果、削る前のサドルは以下のような状態でした。
削る前のサドルの寸法
1弦側<6.1mm> 6弦側<8.0mm>
ちなみに測定には『ノギス』を使います。

本尺目盛りと副尺目盛りを組み合わせることにより、最小で<0.05mm>まで読み取ることが出来ます。サドルを削る量は<0.4mm>と、1mm以下を正確に測る必要がありますので。やはり、ノギスを使った方が良いですね。
削る量が<0.4mm>なので、サドルの目標数値は以下のようになります。
1弦側 6.1-0.4 = <5.7mm>
6弦側 8.0-0.4 = <7.6mm>
上記の数値目指して、手順⑤ サドルを削ります!
削る時に使うものは、100番・180番・240番のサンドペーパー。そして、しっかり平らな面を出す為に、強化ガラスを台に使用しました。

で、あとは、手の感覚に全てをゆだね、ゆっくりとサドル底面を削っていきます。

始めは180番のサンドペーパーで削っていましたが、サドルって結構硬いんです。全然削れていかないので、最初の『慎重に丁寧に』の合言葉も忘れ、100番でガシガシと削りました。
ただ、時々、サドルの底面をガラスに当ててみて『均等に削れているかを確認』します。問題の底面の角度については、本当に手の感覚が頼りでしたが、何とか上手くいきそうです。自分の手は工業用ロボットだと言い聞かせ、削る前の角度を変えないように固定し、注意しながら削った訳です。
で、『ある程度削ったら測定』を繰り返しました。
この一連の、『均等に削れているかの確認』と『ある程度削ったら測定』は、面倒に思わずにマメにやった方が良いと思います。それと、もしサドルの底面が斜めではなく平らだったら、サンドペーパーに『直角』に当てることと、『直角をキープできているかの確認』も怠ってはいけません。まぁ、今回はこの確認が必要ありませんでしたが・・・。
さぁ、とうとうサドルの厚さが目標の数値に近付きました。ここからは、サンドペーパーを180番に変えます。微調整ですね。シャカシャカシャカ・・・
で、とうとう、目標の数値に到達。時間にして15分ぐらいでしたので、思ったほど時間は掛かりませんでした。
削った後のサドルの測定です。
1弦側<5.7mm> 6弦側<7.5mm>
あれ?1弦側は目標にピッタリですが、6弦側は<0.1mm>削り過ぎですね・・・。
まぁ、この程度なら大丈夫だと思いますので・・・続行いたします。
手順⑦ サドルをギターにセットし弦を張ってチューニングしたあと弦高を測ります。
この時、弦はギターのペグの部分に巻いたままになっていますので、それほど手間を掛けずに弦を張ることができます。で、チューニングしました。
弦高を測定してみます。ドキドキ・・・
出ました!
1弦

シックネスゲージの<1.0mm>と<0.7mm>の組み合わせでピッタリ!
という事は、目標の<1.7mm>丁度です!
6弦

ゲージの<1.0mm>と<0.9mm>と<0.5mm>の組み合わせでピッタリ!ということは・・えっと・・・
<2.4mm>で、目標よりもやはり<0.1mm>低くなりました。まぁ、問題ないでしょう。
という訳で、一回で目標の弦高を(だいたい)達成できました!
もしこの時点で弦高が目標の数値に到達していなかったら、もう一度ギターからサドルを外して、削って、戻して、弦を張って・・・とやらなければなりません。
最初の①②での測定と計算。そして、⑤⑥のサドルを削りながらマメにチェック。この手順がとても大切だということですね。
さて、これで一応、私の初めての弦高調整が終わりました。
サドルの底面が斜めだと分かった時には、ちょっとビビリましたが。結果的には、その斜めの角度をほぼ正確に保ったまま削れたと思います。私の手の感覚もなかなか。
今回の弦高調整に掛かった時間は、合計で1時間30分ぐらいだと思います。
やる前は、とても気を使う大変な作業かと思っていましたが、ある程度の器具を準備して、測定の部分で手を抜かずにしっかりやれば、意外と簡単な作業でした。
そして、大事な弾き心地ですけど・・・続く。
☆記事に登場した機材をAmazonで見る!
豊光 26枚シックネスゲージ ビニールポーチ入リ M240M


シンワ測定 高級ミニノギス 100mm


☆関連記事
・ヤマハ エレアコギター APX700II
・ヤマハ エレアコギター APX700II の弦高調整
・ヤマハ エレアコギター APX700II の弦高調整2
・ヤマハ エレアコギター APX700II の弦高調整後の弾き心地
・ヤマハ エレアコギター APX700IIにコンデンサーマイクCM-1を付ける!
・ピエゾ+コンデンサーマイクCM-1の音の検証
☆厳選!ギターを始めたばかりの方にお勧めの記事3つ!
厳選1 メロディ演奏にもコード伴奏にも密接な関連があるCメジャースケール。ギターを初めて触った時から上級者になるまでの練習の必須項目!
【Cメジャースケールを練習しよう!~ギターにおけるCメジャースケールの重要性~】
厳選2 ギターで最初に練習するべき曲は教則本には載っていない場合が多いんです!最初にどんな曲を弾くべきか?またその判別方法は?
【ギターで最初に挑戦する曲は?~キィの判別と教則本の落とし穴~】
厳選3 sinyaが猛烈プッシュするギターの新しい練習方法!いずれは、この練習がギターリストにとっての当たり前になると本気で思っています。ギターの全てが詰まった画期的な練習です!
【ギターリストの新しい練習方法~二胡譜の活用~】


【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!
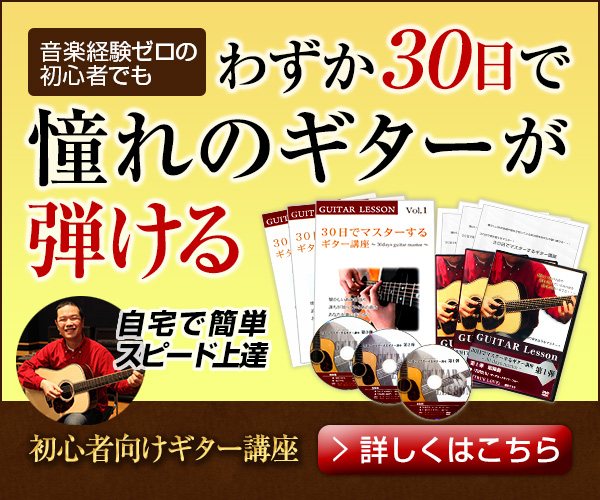

APX700から外したサドルの底面が、斜めだった件。写真では分かり難かったので、図で説明します。
従来のサドルは、底面が平らです。なので、底面を削る時には、サドルをサンドペーパーに『直角』に当てます。削っている最中にも、時々その『直角』を確認することによって、底面が平らに削られているかどうかの判断をする訳です。
ところが、APX700は図の右のように、サドルの底面が斜めになっていました。これでは、サンドペーパーに『直角』に当てることは出来ません。『直角』に当てることが出来ないということは、平らに削られているかどうかの判断材料を失ってしまうことになります。
とはいえ、いてもたっていられずに始めた作業なので、ここで止めるのも悔しいし、今から新しいサドルを注文して届くまで待てる自信もありません。
で、考えられる案は2つ。
第一案・・・斜めになっている部分を削って平らにしてしまう。
第二案・・・斜めのまま削る。
APX700のサドルの底面が、なぜ斜めになっているのか?その理由は分かりません。ただ、もちろん意味があってのことだと思います。なので、出来れば斜めの状態を保ちたい。
そして、第一案のように斜めの部分をカットしてしまうと、予定の削る量を大幅にオーバーしてしまいます。サドルの底を削る量は、前回の計算では<0.4mm>です。斜めの部分をカットしたら、恐らくその倍は削れてしまいます。
そんなに削ったら、弦高が低くなり過ぎて、音に支障が出てしまうと思います。
という訳で、第二案を決行いたします。
『直角』があてにならない以上、削る前の斜めの角度を保ちながら削る他ありません。
しかし、斜めの角度を正確に保ちながら底面を削る方法が思い浮かばないので、全てを『自分の手の感覚』にゆだねることにしました。
う~ん、職人さんみたいでカッコイイです。もう一度言います、私、アコギの弦高調整は初めてです。
そうと決まりましたので。作業を続行いたします。
前回、手順③までいきましたので、手順④ 削る前のサドルを測定します。
サドルは、真っ白い部品です。そのままでは、どこを基点に測定して良いのか分かりません。なので、計測の基点となる線をマジックで入れます。これは、1弦と6弦の当たる位置の2箇所で良いと思います。が、何となく1弦~6弦の全6箇所に印を付けてしまいました。

この計測基点を元に測ります。

測定の結果、削る前のサドルは以下のような状態でした。
削る前のサドルの寸法
1弦側<6.1mm> 6弦側<8.0mm>
ちなみに測定には『ノギス』を使います。

本尺目盛りと副尺目盛りを組み合わせることにより、最小で<0.05mm>まで読み取ることが出来ます。サドルを削る量は<0.4mm>と、1mm以下を正確に測る必要がありますので。やはり、ノギスを使った方が良いですね。
削る量が<0.4mm>なので、サドルの目標数値は以下のようになります。
1弦側 6.1-0.4 = <5.7mm>
6弦側 8.0-0.4 = <7.6mm>
上記の数値目指して、手順⑤ サドルを削ります!
削る時に使うものは、100番・180番・240番のサンドペーパー。そして、しっかり平らな面を出す為に、強化ガラスを台に使用しました。

で、あとは、手の感覚に全てをゆだね、ゆっくりとサドル底面を削っていきます。

始めは180番のサンドペーパーで削っていましたが、サドルって結構硬いんです。全然削れていかないので、最初の『慎重に丁寧に』の合言葉も忘れ、100番でガシガシと削りました。
ただ、時々、サドルの底面をガラスに当ててみて『均等に削れているかを確認』します。問題の底面の角度については、本当に手の感覚が頼りでしたが、何とか上手くいきそうです。自分の手は工業用ロボットだと言い聞かせ、削る前の角度を変えないように固定し、注意しながら削った訳です。
で、『ある程度削ったら測定』を繰り返しました。
この一連の、『均等に削れているかの確認』と『ある程度削ったら測定』は、面倒に思わずにマメにやった方が良いと思います。それと、もしサドルの底面が斜めではなく平らだったら、サンドペーパーに『直角』に当てることと、『直角をキープできているかの確認』も怠ってはいけません。まぁ、今回はこの確認が必要ありませんでしたが・・・。
さぁ、とうとうサドルの厚さが目標の数値に近付きました。ここからは、サンドペーパーを180番に変えます。微調整ですね。シャカシャカシャカ・・・
で、とうとう、目標の数値に到達。時間にして15分ぐらいでしたので、思ったほど時間は掛かりませんでした。
削った後のサドルの測定です。
1弦側<5.7mm> 6弦側<7.5mm>
あれ?1弦側は目標にピッタリですが、6弦側は<0.1mm>削り過ぎですね・・・。
まぁ、この程度なら大丈夫だと思いますので・・・続行いたします。
手順⑦ サドルをギターにセットし弦を張ってチューニングしたあと弦高を測ります。
この時、弦はギターのペグの部分に巻いたままになっていますので、それほど手間を掛けずに弦を張ることができます。で、チューニングしました。
弦高を測定してみます。ドキドキ・・・
出ました!
1弦

シックネスゲージの<1.0mm>と<0.7mm>の組み合わせでピッタリ!
という事は、目標の<1.7mm>丁度です!
6弦

ゲージの<1.0mm>と<0.9mm>と<0.5mm>の組み合わせでピッタリ!ということは・・えっと・・・
<2.4mm>で、目標よりもやはり<0.1mm>低くなりました。まぁ、問題ないでしょう。
という訳で、一回で目標の弦高を(だいたい)達成できました!
もしこの時点で弦高が目標の数値に到達していなかったら、もう一度ギターからサドルを外して、削って、戻して、弦を張って・・・とやらなければなりません。
最初の①②での測定と計算。そして、⑤⑥のサドルを削りながらマメにチェック。この手順がとても大切だということですね。
さて、これで一応、私の初めての弦高調整が終わりました。
サドルの底面が斜めだと分かった時には、ちょっとビビリましたが。結果的には、その斜めの角度をほぼ正確に保ったまま削れたと思います。私の手の感覚もなかなか。
今回の弦高調整に掛かった時間は、合計で1時間30分ぐらいだと思います。
やる前は、とても気を使う大変な作業かと思っていましたが、ある程度の器具を準備して、測定の部分で手を抜かずにしっかりやれば、意外と簡単な作業でした。
そして、大事な弾き心地ですけど・・・続く。
☆記事に登場した機材をAmazonで見る!
豊光 26枚シックネスゲージ ビニールポーチ入リ M240M

シンワ測定 高級ミニノギス 100mm

☆関連記事
・ヤマハ エレアコギター APX700II
・ヤマハ エレアコギター APX700II の弦高調整
・ヤマハ エレアコギター APX700II の弦高調整2
・ヤマハ エレアコギター APX700II の弦高調整後の弾き心地
・ヤマハ エレアコギター APX700IIにコンデンサーマイクCM-1を付ける!
・ピエゾ+コンデンサーマイクCM-1の音の検証
☆厳選!ギターを始めたばかりの方にお勧めの記事3つ!
厳選1 メロディ演奏にもコード伴奏にも密接な関連があるCメジャースケール。ギターを初めて触った時から上級者になるまでの練習の必須項目!
【Cメジャースケールを練習しよう!~ギターにおけるCメジャースケールの重要性~】
厳選2 ギターで最初に練習するべき曲は教則本には載っていない場合が多いんです!最初にどんな曲を弾くべきか?またその判別方法は?
【ギターで最初に挑戦する曲は?~キィの判別と教則本の落とし穴~】
厳選3 sinyaが猛烈プッシュするギターの新しい練習方法!いずれは、この練習がギターリストにとっての当たり前になると本気で思っています。ギターの全てが詰まった画期的な練習です!
【ギターリストの新しい練習方法~二胡譜の活用~】


【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!
2013年02月02日
ヤマハ エレアコギター APX700II の弦高調整
⇒【sinyaが開発!弾く脳トレ!よなおしギター】
昨日の今日ですが、いてもたってもいられず、買ったばかりのAPX700の弦高調整にチャレンジしてみることにしました。
先に宣言しておきます。私、今までアコギの弦高調整はやったことがありません。なので、ネットや本などを参考に『私独自のやり方』で決行いたします。
もし参考になさる場合は、その点をご理解の上、十分に注意してから決行してください。
今回、アコギの弦高調整(弦高を低くする調整)は、一般的な『サドルの底面を削る』方法でトライです。
サドルとは、ブリッジ部についている白いこれです。

本来は、アコギ用のサドルを別に購入してから調整を行うのがベストです。一度削ってしまえば、もう元に戻りませんので。万が一、ギターに付いているサドルを使って失敗してしまったら・・・大変です。
ただ、私、いてもたってもいられず、買ったばかりのAPX700に付いているサドルを削っちゃうことにしました。
『慎重に丁寧に』を合言葉に、ミスをしないように細心の注意を払って決行いたします。
では、まず手順から。
①今のギターの状態を知る
・チューニングした状態で弦高を測ります。
・測るのは『6弦12フレット』と『1弦12フレット』の2箇所。
・測った数値はしっかりメモを取っておきます。
②目標の弦高を決めサドルを何ミリ削るか計算する
・目標となる弦高を決めてメモを取ります。
・<今の弦高-目標の弦高×2> が、削るサドルの厚さになります。
③ギター本体からサドルを外す
④削る前の状態のサドルを測定する
⑤サドルの底面を削る
・この時、サドルが『平らに』削れているかをマメにチェックします。
⑥サドルの厚さを測りどれくらい削れたかを確認する
⑦サドルをギターにセットし弦を張ってチューニングしたあと弦高を測る
⑧目標の弦高になるまで⑤⑥⑦を繰り返す
弦高調整は①と②がとても大事です。ここをおろそかにすると、大変なことになりますので。①と②で調整の良し悪しが決まると思っていただいても良いです。
で、①②での注意点は、必ず『チューニングした状態で弦高を測ること』です。
前回の記事で、アストリアス『ソロスタンダード』の弦高が1弦<1.5mm>と書きましたが、大きな間違いでした。アストリアスの弦を『ペグ半周分ゆるめていた』ことをスッカリ忘れていたんです。
で、改めて今日、チューニングした状態のアストリアスを測りましたら、1弦<1.7mm>でした。
これは、弦を張ることによって弦の張力により少しずつネックが『順反り』状態になることによって起きる現象です。弦を強く張れば張るほど、弦とネックが離れていき、弦高が高くなる訳です。
昨日は、アストリアスの弦をゆるめた状態で測定したので、チューニングした状態よりも弦高が低かったことになります。
いくらなんでも低すぎるな~と、思ってはいたんですが・・・。
さて、注意点が分かったところで、①②の作業を決行いたします。
まず、測定結果と目標数値は下記のようになりました。
現状の弦高
1弦12フレット<1.9mm>
6弦12フレット<2.7mm>
目標の弦高
1弦12フレット<1.7mm>
6弦12フレット<2.5mm>
現状と目標の差
1弦6弦共に<0.2mm>
削るサドルの厚さ
0.2 × 2 = <0.4mm>
上記のように、サドルの底面を<0.4mm>削ることにしました。
弦高は『シックネスゲージ』で測りました。シックネスゲージとは、さまざまな厚さの薄い金属板を組み合わせて測るものの隙間に挿入し、 その隙間の寸法を測定する工具です。

※使う時は、薄い金属板をバラバラにします。
弦高とは『弦の下の面からフレットの上の面』までの高さのことを言います。ですから、このゲージを弦と12フレットの間に挟んで、丁度ピッタリの金属板の組み合わせを探すことになります。
目標の弦高は、アストリアス『ソロスタンダード』を参考にしました。アストリアスのギターは、弾きやすさと音色の良さを兼ね備えている上、自前のギターの中で一番多く弾いていてその弦高に慣れているんです。
削るサドルの厚さを算出する時に、下げる弦高の数値を2倍(×2)するのは、12フレットが丁度弦の<1/2>の場所になるからです。まぁこの辺りは難しく考えずに、単純に2倍すると覚えましょう。
さて、これでサドルを何ミリ削れば目標の弦高に到達するかが算出されました。で、サドルの底面を削るには、ギターに付いたままでは無理です。
手順③ ギター本体からサドルを外してみましょう。
この作業はとても簡単です。なぜなら、サドルはギター本体にハマっているだけなんです。ですので、弦をゆるめて、サドルを手でつまんでグイッと引っ張れば簡単に取れます。

取れました。
ここで注意する点は、サドルより弦です。弦は、完全に外してしまってはダメなんです。
手順⑦で、弦高の確認の度に、何回も弦を張る必要があるんです。なので、ブリッジ側は外しますが、ペグ側は巻いたままにしておきます。

黒のボディーなので、映り込みがスゴイ・・・カレンダーとか気にしないで下さい。
さて、サドルが外れました。で、良く見ると、何と!サドルの底面が平らではありません!斜めだ!

底面が斜めになっているのが分かりますか?
これは予想外です。本来は、サドルを『直角』にサンドペーパーに当てて底を削ります。その『直角』が、サドルが平らに削られているかどうかの唯一の確認方法になるんです。
しかし、底が斜めのこのサドルでは、サンドペーパーに『直角』に当てることが出来ません・・・
ど~しよう・・・・続く。
☆記事に登場した機材をAmazonで見る!
豊光 26枚シックネスゲージ ビニールポーチ入リ M240M


シンワ測定 高級ミニノギス 100mm


☆関連記事
・ヤマハ エレアコギター APX700II
・ヤマハ エレアコギター APX700II の弦高調整
・ヤマハ エレアコギター APX700II の弦高調整2
・ヤマハ エレアコギター APX700II の弦高調整後の弾き心地
・ヤマハ エレアコギター APX700IIにコンデンサーマイクCM-1を付ける!
・ピエゾ+コンデンサーマイクCM-1の音の検証
☆厳選!ギターを始めたばかりの方にお勧めの記事3つ!
厳選1 メロディ演奏にもコード伴奏にも密接な関連があるCメジャースケール。ギターを初めて触った時から上級者になるまでの練習の必須項目!
【Cメジャースケールを練習しよう!~ギターにおけるCメジャースケールの重要性~】
厳選2 ギターで最初に練習するべき曲は教則本には載っていない場合が多いんです!最初にどんな曲を弾くべきか?またその判別方法は?
【ギターで最初に挑戦する曲は?~キィの判別と教則本の落とし穴~】
厳選3 sinyaが猛烈プッシュするギターの新しい練習方法!いずれは、この練習がギターリストにとっての当たり前になると本気で思っています。ギターの全てが詰まった画期的な練習です!
【ギターリストの新しい練習方法~二胡譜の活用~】


【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!
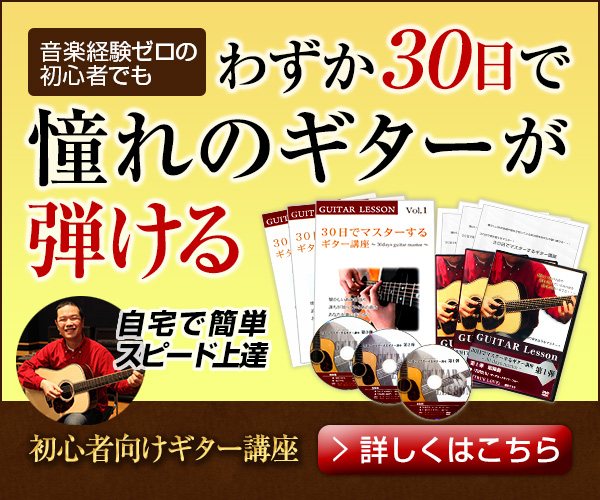

昨日の今日ですが、いてもたってもいられず、買ったばかりのAPX700の弦高調整にチャレンジしてみることにしました。
先に宣言しておきます。私、今までアコギの弦高調整はやったことがありません。なので、ネットや本などを参考に『私独自のやり方』で決行いたします。
もし参考になさる場合は、その点をご理解の上、十分に注意してから決行してください。
今回、アコギの弦高調整(弦高を低くする調整)は、一般的な『サドルの底面を削る』方法でトライです。
サドルとは、ブリッジ部についている白いこれです。
本来は、アコギ用のサドルを別に購入してから調整を行うのがベストです。一度削ってしまえば、もう元に戻りませんので。万が一、ギターに付いているサドルを使って失敗してしまったら・・・大変です。
ただ、私、いてもたってもいられず、買ったばかりのAPX700に付いているサドルを削っちゃうことにしました。
『慎重に丁寧に』を合言葉に、ミスをしないように細心の注意を払って決行いたします。
では、まず手順から。
①今のギターの状態を知る
・チューニングした状態で弦高を測ります。
・測るのは『6弦12フレット』と『1弦12フレット』の2箇所。
・測った数値はしっかりメモを取っておきます。
②目標の弦高を決めサドルを何ミリ削るか計算する
・目標となる弦高を決めてメモを取ります。
・<今の弦高-目標の弦高×2> が、削るサドルの厚さになります。
③ギター本体からサドルを外す
④削る前の状態のサドルを測定する
⑤サドルの底面を削る
・この時、サドルが『平らに』削れているかをマメにチェックします。
⑥サドルの厚さを測りどれくらい削れたかを確認する
⑦サドルをギターにセットし弦を張ってチューニングしたあと弦高を測る
⑧目標の弦高になるまで⑤⑥⑦を繰り返す
弦高調整は①と②がとても大事です。ここをおろそかにすると、大変なことになりますので。①と②で調整の良し悪しが決まると思っていただいても良いです。
で、①②での注意点は、必ず『チューニングした状態で弦高を測ること』です。
前回の記事で、アストリアス『ソロスタンダード』の弦高が1弦<1.5mm>と書きましたが、大きな間違いでした。アストリアスの弦を『ペグ半周分ゆるめていた』ことをスッカリ忘れていたんです。
で、改めて今日、チューニングした状態のアストリアスを測りましたら、1弦<1.7mm>でした。
これは、弦を張ることによって弦の張力により少しずつネックが『順反り』状態になることによって起きる現象です。弦を強く張れば張るほど、弦とネックが離れていき、弦高が高くなる訳です。
昨日は、アストリアスの弦をゆるめた状態で測定したので、チューニングした状態よりも弦高が低かったことになります。
いくらなんでも低すぎるな~と、思ってはいたんですが・・・。
さて、注意点が分かったところで、①②の作業を決行いたします。
まず、測定結果と目標数値は下記のようになりました。
現状の弦高
1弦12フレット<1.9mm>
6弦12フレット<2.7mm>
目標の弦高
1弦12フレット<1.7mm>
6弦12フレット<2.5mm>
現状と目標の差
1弦6弦共に<0.2mm>
削るサドルの厚さ
0.2 × 2 = <0.4mm>
上記のように、サドルの底面を<0.4mm>削ることにしました。
弦高は『シックネスゲージ』で測りました。シックネスゲージとは、さまざまな厚さの薄い金属板を組み合わせて測るものの隙間に挿入し、 その隙間の寸法を測定する工具です。

※使う時は、薄い金属板をバラバラにします。
弦高とは『弦の下の面からフレットの上の面』までの高さのことを言います。ですから、このゲージを弦と12フレットの間に挟んで、丁度ピッタリの金属板の組み合わせを探すことになります。
目標の弦高は、アストリアス『ソロスタンダード』を参考にしました。アストリアスのギターは、弾きやすさと音色の良さを兼ね備えている上、自前のギターの中で一番多く弾いていてその弦高に慣れているんです。
削るサドルの厚さを算出する時に、下げる弦高の数値を2倍(×2)するのは、12フレットが丁度弦の<1/2>の場所になるからです。まぁこの辺りは難しく考えずに、単純に2倍すると覚えましょう。
さて、これでサドルを何ミリ削れば目標の弦高に到達するかが算出されました。で、サドルの底面を削るには、ギターに付いたままでは無理です。
手順③ ギター本体からサドルを外してみましょう。
この作業はとても簡単です。なぜなら、サドルはギター本体にハマっているだけなんです。ですので、弦をゆるめて、サドルを手でつまんでグイッと引っ張れば簡単に取れます。

取れました。
ここで注意する点は、サドルより弦です。弦は、完全に外してしまってはダメなんです。
手順⑦で、弦高の確認の度に、何回も弦を張る必要があるんです。なので、ブリッジ側は外しますが、ペグ側は巻いたままにしておきます。

黒のボディーなので、映り込みがスゴイ・・・カレンダーとか気にしないで下さい。
さて、サドルが外れました。で、良く見ると、何と!サドルの底面が平らではありません!斜めだ!

底面が斜めになっているのが分かりますか?
これは予想外です。本来は、サドルを『直角』にサンドペーパーに当てて底を削ります。その『直角』が、サドルが平らに削られているかどうかの唯一の確認方法になるんです。
しかし、底が斜めのこのサドルでは、サンドペーパーに『直角』に当てることが出来ません・・・
ど~しよう・・・・続く。
☆記事に登場した機材をAmazonで見る!
豊光 26枚シックネスゲージ ビニールポーチ入リ M240M

シンワ測定 高級ミニノギス 100mm

☆関連記事
・ヤマハ エレアコギター APX700II
・ヤマハ エレアコギター APX700II の弦高調整
・ヤマハ エレアコギター APX700II の弦高調整2
・ヤマハ エレアコギター APX700II の弦高調整後の弾き心地
・ヤマハ エレアコギター APX700IIにコンデンサーマイクCM-1を付ける!
・ピエゾ+コンデンサーマイクCM-1の音の検証
☆厳選!ギターを始めたばかりの方にお勧めの記事3つ!
厳選1 メロディ演奏にもコード伴奏にも密接な関連があるCメジャースケール。ギターを初めて触った時から上級者になるまでの練習の必須項目!
【Cメジャースケールを練習しよう!~ギターにおけるCメジャースケールの重要性~】
厳選2 ギターで最初に練習するべき曲は教則本には載っていない場合が多いんです!最初にどんな曲を弾くべきか?またその判別方法は?
【ギターで最初に挑戦する曲は?~キィの判別と教則本の落とし穴~】
厳選3 sinyaが猛烈プッシュするギターの新しい練習方法!いずれは、この練習がギターリストにとっての当たり前になると本気で思っています。ギターの全てが詰まった画期的な練習です!
【ギターリストの新しい練習方法~二胡譜の活用~】


【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!
2013年01月25日
ストラップロックピン~ライブでの失敗例と対処法~
⇒【sinyaが開発!弾く脳トレ!よなおしギター】
教室の生徒さんの中には、すでにバンドを組んで活動を始めている方が何人かいらっしゃいます。
自分も、バンド活動の経験は長いため、演奏的なこと以外でのアドバイスもさせて頂いています。
バンドを組んだら、やっぱりライブが目標となる場合が多いですよね。ただ、正直に言いますと、スタジオ練習とライブとでは、雲泥の差があります。
スタジオで上手く演奏できたものをそのままライブでパフォーマンス出来るまでには、それ相当の経験が必要になるでしょう。バンドを組んで最初のライブは『失敗する』と、ある意味、覚悟しておいた方が良いと思います。
ただ、この『失敗』は、バンドをやる人間なら誰でも経験することです。なので、恐れる必要はまったくありません。大切なことは、『1度失敗したことを次には失敗しないこと』です。
そのためにどうしたら良いのか、その解決方法は一つしかありません。『準備』です。
ライブの『失敗』というと、コードを間違えたとかソロで音を外したとか、演奏面の失敗が主だと思うかもしれませんが、実は違います。演奏面の失敗は、ある程度ライブを経験してもやっちゃいます。私も、未だに時々やらかします。
もちろん、完璧な演奏をするに越したことはありません。が、演奏面の失敗は、ある程度なら誤魔化してカヴァーできます。極端に言ってしまえば、お客さんが間違いに気付かなければ、それは『失敗』ではありませんので。
スタジオや自宅練習で、曲を完璧に演奏できるようにするのは絶対ですが、ライブではパフォーマンスの方が大事な場合もあります。演奏が完璧でも、ライブで突っ立ったままでは見ていて面白くないし。演奏が雑でも、パフォーマンスがカッコ良ければ見ている方もノッテくる。ライブとはそんなもんです。
では、私が言うところの『失敗』とは何の事かといいますと・・・
ここで、私の経験、あるいは、私が見てきたバンドの実際の失敗を列挙してみます。その方が実感すると思います。
①私も経験がありますが、機材のトラブル。スタジオ練習の時には全く問題が無かったのに『ライブで音が出ない』ことはよくあります。
②ライブ中にギターの弦が切れる。私は経験がありませんが、これをやる人は、毎回決まって弦を切ります。
③ギターリスト用のマイクスタンドが演奏中に曲がる。演奏中に手が使えないギターリストは、マイクスタンドが倒れてきても直せないので、非常に困る上、そのマイクスタンドの動きの面白さに観客が演奏そっちのけで釘付けになります。
④ピックが落ちる。曲が終わるまで指で弾かなければなりませんね。たぶん、落としたピックを暗いステージ上で探して拾うのは至難の業です。
⑤カンペ(曲の演奏順や不安なコード進行などを書いた紙)が、ライブ中のライティング(逆光や暗がり)で全く見えない。困る・・・。
⑥シールド(ギターと機材を繋ぐコード)を踏んでしまうなどして抜いてしまう。全く音が出なくなります。
⑦ストラップが抜けてしまう。ギターが全く弾けなくなります。
今思いつくものを列挙しましたが、これはギターリストだけのことです。メンバーの中で最も『失敗』が多いのは、ドラムだと思います。が、ギターだけ見ても、ここにあげた7つよりもっと多くの『失敗』が考えられると思います。
①から、簡単に対処方法を書いてみます。
①機材のトラブルの原因は、主に『電池切れ』『シールド断線』『シールド接続不良』『機材故障』『ギター内電気系統の故障』あたりだと思います。
『電池切れ』・・ライブ前、電池を使っている機材はなるべく新しいものに替える。電池の予備を準備する。パワーサプライを使い電池を使わないシステムを作る。
『シールド断線』・・シールドは必ず予備を準備。仕舞う時は常に八の字巻き。
『シールド接続不良』・・ステージ直前にシールドが各機材に奥までしっかり入っているか確認。
『機材故障』・・練習中に不安定だった機材はライブでは使わない。
『ギター内電気系統の故障』・・練習中にギターからバリバリとノイズが出る場合は、ライブ前に直しておく。
②弦が切れる原因は2つ。『弦が古い』『力みすぎ』。
『弦が古い』・・問題外。ライブ直前のスタジオ練習までには新しい弦を張る。
『力みすぎ』・・弦が切れる理由は圧倒的にこっちの方が多いと思います。これはクセなので、切る人は決まっているんです。ハッキリ言いますと『弦を切る人=ギターが永遠に上手くならない人』です。頑張って練習して、力が抜けたピッキングをマスターしましょう。そして、ライブの時に興奮しすぎないように・・・。
③マイクスタンドのネジ部分を、ライブ直前に忘れずにしっかり閉める。
④予備のピックを直ぐに取れる場所に準備しておく。私はやりませんが、マイクスタンドやギター本体にピックを付けるツールもあります。
⑤ライブまでにはコード進行などをしっかり覚えるのがまず基本となりますが、曲順などは忘れガチ。カンペは、モニター(自分やメンバーの音を聞くためのスピーカーで、ステージの一番前に置いてあることがほとんど)に貼ると本番には暗くなるので見え難い場合が多いです。床に貼る場合も、暗くなる場所は避けます。ギターリストは、ステージの右か左に寄る場合が多いので、寄る方の壁の目線の高さに貼ると見やすかったりします。いずれにしろ、本番のライティングを考えてから貼りましょう。
⑥本番直前のセッティングの時、シールドの取り回しに十分気を付ける。あまりメンバーや自分が立ち入らない場所に取り回しましょう。なので、あまり短いシールドは不可。かといって長すぎてもノイズの問題があるので、シールドはステージにあった長さを選びましょう。
昔からよく使われている方法で、ギターから出たシールドをそのまま垂らすのではなく、ストラップとギター本体の間を通してから機材に繋ぐ方法があります。シールド抜け防止には、簡単で効果が大きいです。

そして⑦ 実は、今日挙げた失敗例で最も悲惨だったのがこれです。私ではないのですが・・・。
本番中にギターボーカルのストラップが外れる→ギター演奏を止め歌いながら膝にギターを乗せて直そうとするも焦って直らず→ギターが膝から滑り落ち→滑り落ちたギターが自分のマイクスタンドに直撃→マイクスタンドが観客席に倒れ込む→ギターボーカルなのにギターもマイクも失う・・・。
もう、可愛そうで見ていられませんでした。
ギターリストは、ギターを失ってしまったらただのリストです。ライブ中にストラップが絶対に外れないように準備しましょう。
対処方法はいくつかあります。ストラップを厚い皮のしっかりしたものにするのも有効ですが、革はいずれ柔らかくなってしまいます。私は、ストラップをギターにセットした状態で、ストラップの穴をテープでグルグル巻きにしたりします。今日のミュージックステーションで、『モンゴル800』のギターの人は、やはりストラップとギターをテープでグルグル巻きにしていましたね。あそこまですると、さすがに見た目で抵抗のある人もいると思います。ストラップだけを穴が広がらないようにテープで巻くだけでも十分に効果があります。

そして、ギターのストラップ抜け防止で最も効果的なのが『ストラップロックピン』です。
これは、ギター本体のストラップピンを外して、新しくゴツイ金具を取り付けなければならないので、少しだけ勇気が要ります。が、ライブ中にギターを失うよりは何百倍もマシです。
で、ストラップにも金具を取り付けます。ギターに付けたゴツイ金具とストラップにつけた金具をカチッと合体させると、もう絶対にギターとストラップが離れることはありません。ストラップを外したい場合は、メーカーによってもやり方が違いますが、ストラップ側の金具にボタンが付いていて、それを押したり引いたりすことによって外すことができます。
ストラップが外れないようにするには効果絶大ですので、お勧めです。
Amazonで見る↓
Schaller シャーラー ストラップロックピン 14010201 (#446) Chrome クローム


さて、以上のように、ライブではホントにイロイロな『失敗』を想定して準備しておかなければなりません。不安材料が少しでもあると、演奏・パフォーマンスに集中できないんです。
もし、ライブ本番中にこれら『失敗』の1つでも発生したら、ステージ上では絶対に対応できないと思って下さい。普段は簡単に出来るとしても、ステージ上で同じように簡単に出来るということは絶対にあり得ません。
ライブ会場に到着したら、演奏のことは考える暇がないと思って下さい。『失敗』しない為の準備を絶対に怠らないで下さい。二度三度と何重にも確認してください。
そうやって不安材料を一つ一つ消していくことによって、本番は思いっきりパフォーマンスが出来る訳です。カッコいいステージを見せたければ、本番前に曲の練習をしていては絶対に駄目です。今までたくさん練習してきました。それを信じて、本番前は指のウォーミングアップ程度で十分です。『失敗を無くす準備』に全てを注ぎ込みましょう。
しつこいですよね。でもそれが、最高のパフォーマンスをする為の最低条件となります。
☆厳選!ギターを始めたばかりの方にお勧めの記事3つ!
厳選1 メロディ演奏にもコード伴奏にも密接な関連があるCメジャースケール。ギターを初めて触った時から上級者になるまでの練習の必須項目!
【Cメジャースケールを練習しよう!~ギターにおけるCメジャースケールの重要性~】
厳選2 ギターで最初に練習するべき曲は教則本には載っていない場合が多いんです!最初にどんな曲を弾くべきか?またその判別方法は?
【ギターで最初に挑戦する曲は?~キィの判別と教則本の落とし穴~】
厳選3 sinyaが猛烈プッシュするギターの新しい練習方法!いずれは、この練習がギターリストにとっての当たり前になると本気で思っています。ギターの全てが詰まった画期的な練習です!
【ギターリストの新しい練習方法~二胡譜の活用~】


【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!
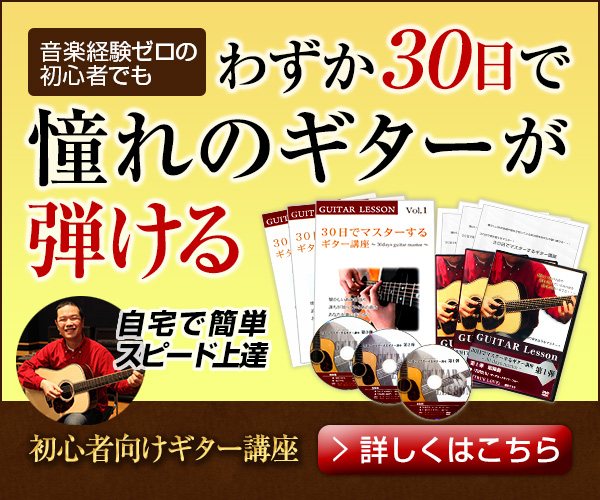

教室の生徒さんの中には、すでにバンドを組んで活動を始めている方が何人かいらっしゃいます。
自分も、バンド活動の経験は長いため、演奏的なこと以外でのアドバイスもさせて頂いています。
バンドを組んだら、やっぱりライブが目標となる場合が多いですよね。ただ、正直に言いますと、スタジオ練習とライブとでは、雲泥の差があります。
スタジオで上手く演奏できたものをそのままライブでパフォーマンス出来るまでには、それ相当の経験が必要になるでしょう。バンドを組んで最初のライブは『失敗する』と、ある意味、覚悟しておいた方が良いと思います。
ただ、この『失敗』は、バンドをやる人間なら誰でも経験することです。なので、恐れる必要はまったくありません。大切なことは、『1度失敗したことを次には失敗しないこと』です。
そのためにどうしたら良いのか、その解決方法は一つしかありません。『準備』です。
ライブの『失敗』というと、コードを間違えたとかソロで音を外したとか、演奏面の失敗が主だと思うかもしれませんが、実は違います。演奏面の失敗は、ある程度ライブを経験してもやっちゃいます。私も、未だに時々やらかします。
もちろん、完璧な演奏をするに越したことはありません。が、演奏面の失敗は、ある程度なら誤魔化してカヴァーできます。極端に言ってしまえば、お客さんが間違いに気付かなければ、それは『失敗』ではありませんので。
スタジオや自宅練習で、曲を完璧に演奏できるようにするのは絶対ですが、ライブではパフォーマンスの方が大事な場合もあります。演奏が完璧でも、ライブで突っ立ったままでは見ていて面白くないし。演奏が雑でも、パフォーマンスがカッコ良ければ見ている方もノッテくる。ライブとはそんなもんです。
では、私が言うところの『失敗』とは何の事かといいますと・・・
ここで、私の経験、あるいは、私が見てきたバンドの実際の失敗を列挙してみます。その方が実感すると思います。
①私も経験がありますが、機材のトラブル。スタジオ練習の時には全く問題が無かったのに『ライブで音が出ない』ことはよくあります。
②ライブ中にギターの弦が切れる。私は経験がありませんが、これをやる人は、毎回決まって弦を切ります。
③ギターリスト用のマイクスタンドが演奏中に曲がる。演奏中に手が使えないギターリストは、マイクスタンドが倒れてきても直せないので、非常に困る上、そのマイクスタンドの動きの面白さに観客が演奏そっちのけで釘付けになります。
④ピックが落ちる。曲が終わるまで指で弾かなければなりませんね。たぶん、落としたピックを暗いステージ上で探して拾うのは至難の業です。
⑤カンペ(曲の演奏順や不安なコード進行などを書いた紙)が、ライブ中のライティング(逆光や暗がり)で全く見えない。困る・・・。
⑥シールド(ギターと機材を繋ぐコード)を踏んでしまうなどして抜いてしまう。全く音が出なくなります。
⑦ストラップが抜けてしまう。ギターが全く弾けなくなります。
今思いつくものを列挙しましたが、これはギターリストだけのことです。メンバーの中で最も『失敗』が多いのは、ドラムだと思います。が、ギターだけ見ても、ここにあげた7つよりもっと多くの『失敗』が考えられると思います。
①から、簡単に対処方法を書いてみます。
①機材のトラブルの原因は、主に『電池切れ』『シールド断線』『シールド接続不良』『機材故障』『ギター内電気系統の故障』あたりだと思います。
『電池切れ』・・ライブ前、電池を使っている機材はなるべく新しいものに替える。電池の予備を準備する。パワーサプライを使い電池を使わないシステムを作る。
『シールド断線』・・シールドは必ず予備を準備。仕舞う時は常に八の字巻き。
『シールド接続不良』・・ステージ直前にシールドが各機材に奥までしっかり入っているか確認。
『機材故障』・・練習中に不安定だった機材はライブでは使わない。
『ギター内電気系統の故障』・・練習中にギターからバリバリとノイズが出る場合は、ライブ前に直しておく。
②弦が切れる原因は2つ。『弦が古い』『力みすぎ』。
『弦が古い』・・問題外。ライブ直前のスタジオ練習までには新しい弦を張る。
『力みすぎ』・・弦が切れる理由は圧倒的にこっちの方が多いと思います。これはクセなので、切る人は決まっているんです。ハッキリ言いますと『弦を切る人=ギターが永遠に上手くならない人』です。頑張って練習して、力が抜けたピッキングをマスターしましょう。そして、ライブの時に興奮しすぎないように・・・。
③マイクスタンドのネジ部分を、ライブ直前に忘れずにしっかり閉める。
④予備のピックを直ぐに取れる場所に準備しておく。私はやりませんが、マイクスタンドやギター本体にピックを付けるツールもあります。
⑤ライブまでにはコード進行などをしっかり覚えるのがまず基本となりますが、曲順などは忘れガチ。カンペは、モニター(自分やメンバーの音を聞くためのスピーカーで、ステージの一番前に置いてあることがほとんど)に貼ると本番には暗くなるので見え難い場合が多いです。床に貼る場合も、暗くなる場所は避けます。ギターリストは、ステージの右か左に寄る場合が多いので、寄る方の壁の目線の高さに貼ると見やすかったりします。いずれにしろ、本番のライティングを考えてから貼りましょう。
⑥本番直前のセッティングの時、シールドの取り回しに十分気を付ける。あまりメンバーや自分が立ち入らない場所に取り回しましょう。なので、あまり短いシールドは不可。かといって長すぎてもノイズの問題があるので、シールドはステージにあった長さを選びましょう。
昔からよく使われている方法で、ギターから出たシールドをそのまま垂らすのではなく、ストラップとギター本体の間を通してから機材に繋ぐ方法があります。シールド抜け防止には、簡単で効果が大きいです。
そして⑦ 実は、今日挙げた失敗例で最も悲惨だったのがこれです。私ではないのですが・・・。
本番中にギターボーカルのストラップが外れる→ギター演奏を止め歌いながら膝にギターを乗せて直そうとするも焦って直らず→ギターが膝から滑り落ち→滑り落ちたギターが自分のマイクスタンドに直撃→マイクスタンドが観客席に倒れ込む→ギターボーカルなのにギターもマイクも失う・・・。
もう、可愛そうで見ていられませんでした。
ギターリストは、ギターを失ってしまったらただのリストです。ライブ中にストラップが絶対に外れないように準備しましょう。
対処方法はいくつかあります。ストラップを厚い皮のしっかりしたものにするのも有効ですが、革はいずれ柔らかくなってしまいます。私は、ストラップをギターにセットした状態で、ストラップの穴をテープでグルグル巻きにしたりします。今日のミュージックステーションで、『モンゴル800』のギターの人は、やはりストラップとギターをテープでグルグル巻きにしていましたね。あそこまですると、さすがに見た目で抵抗のある人もいると思います。ストラップだけを穴が広がらないようにテープで巻くだけでも十分に効果があります。
そして、ギターのストラップ抜け防止で最も効果的なのが『ストラップロックピン』です。
これは、ギター本体のストラップピンを外して、新しくゴツイ金具を取り付けなければならないので、少しだけ勇気が要ります。が、ライブ中にギターを失うよりは何百倍もマシです。
で、ストラップにも金具を取り付けます。ギターに付けたゴツイ金具とストラップにつけた金具をカチッと合体させると、もう絶対にギターとストラップが離れることはありません。ストラップを外したい場合は、メーカーによってもやり方が違いますが、ストラップ側の金具にボタンが付いていて、それを押したり引いたりすことによって外すことができます。
ストラップが外れないようにするには効果絶大ですので、お勧めです。
Amazonで見る↓
Schaller シャーラー ストラップロックピン 14010201 (#446) Chrome クローム

さて、以上のように、ライブではホントにイロイロな『失敗』を想定して準備しておかなければなりません。不安材料が少しでもあると、演奏・パフォーマンスに集中できないんです。
もし、ライブ本番中にこれら『失敗』の1つでも発生したら、ステージ上では絶対に対応できないと思って下さい。普段は簡単に出来るとしても、ステージ上で同じように簡単に出来るということは絶対にあり得ません。
ライブ会場に到着したら、演奏のことは考える暇がないと思って下さい。『失敗』しない為の準備を絶対に怠らないで下さい。二度三度と何重にも確認してください。
そうやって不安材料を一つ一つ消していくことによって、本番は思いっきりパフォーマンスが出来る訳です。カッコいいステージを見せたければ、本番前に曲の練習をしていては絶対に駄目です。今までたくさん練習してきました。それを信じて、本番前は指のウォーミングアップ程度で十分です。『失敗を無くす準備』に全てを注ぎ込みましょう。
しつこいですよね。でもそれが、最高のパフォーマンスをする為の最低条件となります。
☆厳選!ギターを始めたばかりの方にお勧めの記事3つ!
厳選1 メロディ演奏にもコード伴奏にも密接な関連があるCメジャースケール。ギターを初めて触った時から上級者になるまでの練習の必須項目!
【Cメジャースケールを練習しよう!~ギターにおけるCメジャースケールの重要性~】
厳選2 ギターで最初に練習するべき曲は教則本には載っていない場合が多いんです!最初にどんな曲を弾くべきか?またその判別方法は?
【ギターで最初に挑戦する曲は?~キィの判別と教則本の落とし穴~】
厳選3 sinyaが猛烈プッシュするギターの新しい練習方法!いずれは、この練習がギターリストにとっての当たり前になると本気で思っています。ギターの全てが詰まった画期的な練習です!
【ギターリストの新しい練習方法~二胡譜の活用~】


【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!