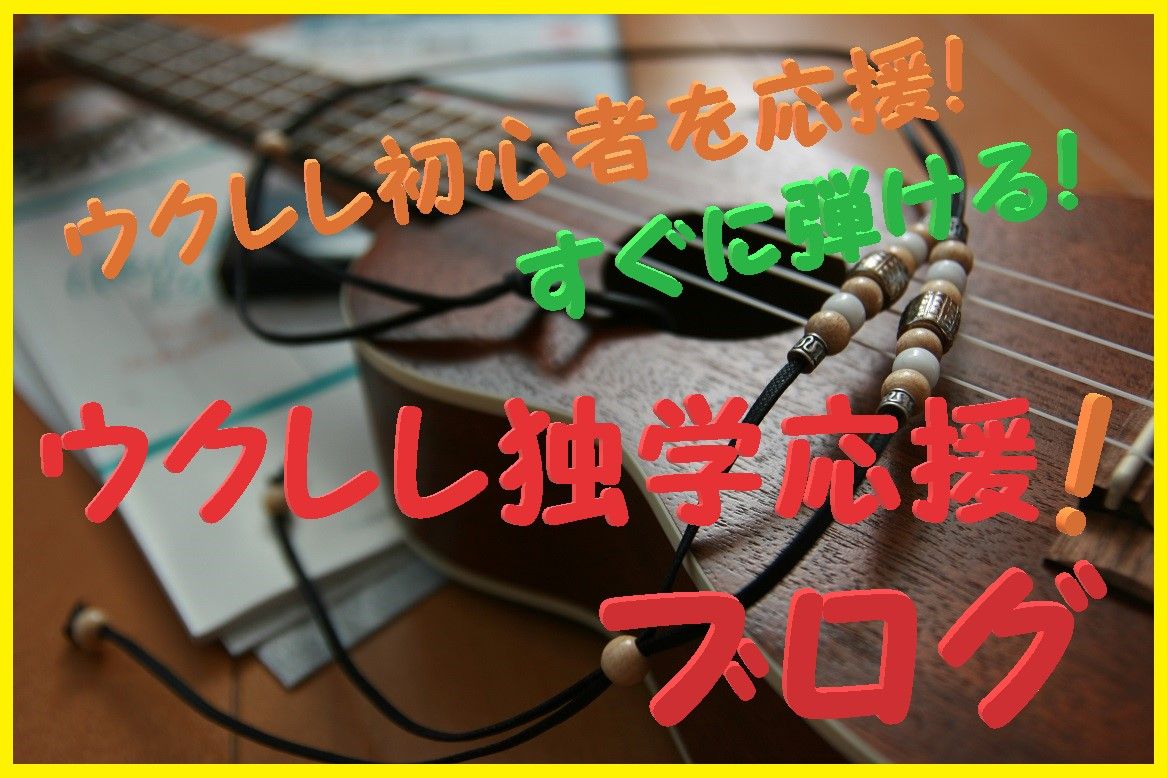2013年02月11日
ヤマハ エレアコギター APX700IIにコンデンサーマイクCM-1を付ける!
⇒【sinyaが開発!弾く脳トレ!よなおしギター】
さて、弦高を下げたことにより、スゴク弾きやすくなったAPX700Ⅱですが、まだ調整は終わっていません。
次は、コンデンサーマイク『CM-1』を取り付ける作業になります。
CM-1については、記事【コムミュージック CM-1】に詳しくい書きましたので、参照して下さい。
確かに、APX700は、もともと付いているピエゾタイプのピックアップだけでもなかなか良い音がします。そのままで良いような気もしますし。でも、物足りない感じもする。
もっと『空気感』を足すことが出来たら、迫力のあるサウンドが得られるような気はしました。
CM-1の取り付けに関しては、とても簡単です。CM-1と一体化したクリップを、ギター本体の『力木』につけるだけです。ただ、あとに書くように、CM-1を取り付けるのには『ある程度の覚悟』が必要です。
なので、本当にCM-1を付ける事によって音は向上するのか?
そこをまず確かめる必要があります。始めはCM-1を『仮に』付けてみて、音がどんな風に変わるのかのチェックです。
で、CM-1を付ける為には、弦が邪魔です。なので、やはり弦高調整の時のようにブリッジピンを抜いて弦を外し、作業をしやすいようにします。
CM-1を取り付けた状態が下の画像です。

この状態から、弦を張って音を出してみました。
やはり、ピエゾ+CM-1の音は、空気感が出て迫力があってGOOD!です。
ピエゾだけで音を鳴らしていた時には、これで良いかもしれないと思いましたが・・・CM-1と一緒に鳴らすと、全然違いますね。この迫力のサウンドは、特にロックを弾くと楽しくて止まらなくなります。
という訳で、本格的にCM-1を取り付けることに決定しました。
そこで、まず問題が1つ。
また上の画像を見てください。CM-1から出ているコードが、サウンドホールからだらしなくビロ~ンと出ていますよね。これでは、ピッキングの邪魔だし、見た目も悪い。さらにこれでは、ハウリング防止の為のサウンドホールカバーが付けられないんです。
そこで、コードの取り回しの仕方も考えなければなりません。
APX700は、エンドピン(ギターの一番下にあるピンで、本来はストラップを付けるためのもの)にピエゾピックアップのコードを繋げるようになっています。で、やはりコード類は近い場所にあった方が扱いやすく、トラブルも少ないのではないかと思い、CM-1のコードもエンドピンの近くから出したい。
要は、CM-1のコードを、ギター本体の中を通して、一番下の『エンドピンの横から出す』ということです。
そして『エンドピンの横から出す』為には、コードを出す為の『穴』を開けなければならない、ということなんです。
ハイ、そこで登場するのがこれ。

ギターの調整には、似つかわしくない道具ですね~。これは、バイクを改造する時に散々使ったドリルです。
実はこれが、上で書いた『ある程度の覚悟』という訳です。
ギターに穴を開けなければならないので、CM-1を付ける事によって音質が向上するという確証が必要だったんですね。
もうその確証は得ましたので、作業を進めていきます。
CM-1のコードの太さは2mm。ドリルの刃の直径を、一回り大きい3.5mmにしました。
ドライバーで、ギター本体にガイドとなるパンチを打ちます。ギター本体が振動しないように慎重に。
そして、ドリルのトリガーを微妙に操作して、少しずつ少しずつドリルを回転させました。バイクの改造とは大違いです。
ドリルをゆっくり回していきましたが、穴は簡単に開きました。幸い、他の場所を傷つけることなくキレイに開けることが出来ました。

さぁ、もうこうなったら後戻りは出来ません。ズンズン作業を進めます。
コードを通す為の穴が開きましたので、コードを通します。
もともとCM-1のコードは非常に長かったので、短くしたいこともあり、バッチリ30cmほどコードを切ってしまいました。
当然、電池ボックスに繋げる為のピンジャックも一緒に取れてしまいますので、新たにピンジャックを購入し、後で取り付ける作戦です。

ここで問題が!
CM-1をギターの力木にクリップで固定するまでは良かったのですが。そこから、コードをギターの一番下まで通そうと、サウンドホールに手を入れたら・・・手が入らない!
APX700のサウンドホールは、独特の楕円形をしています。で、かなり一般的なサウンドホールよりも小さいんですね。私の手では、ボディの半分くらいまでしか手が入らない・・・。とても、穴を開けた一番下までは届きません。
あ~あ、手の小さい妻や息子が帰って来るまで待てないし・・・。
そこで思いつきました。『釣り込み作戦』です。
先ほど切ったコードのあまりを、ギター本体の『外側から』開けた穴に通します。そのコードをギター本体に少しずつ入れていき、CM-1から出ているコードを迎えに行かせます。外側から入れたコードとCM-1から出ているコードをハンダで簡単にくっ付けて、外側から入れたコードを今度はたぐり寄せてきます。すると・・・

ハイ、CM-1のコードが見事に釣れて、ギターの外に出てきました!
この『釣り込み作戦』は、ギターのサウンドに1mmも影響を与えないので、忘れてくださって結構です。
さて、CM-1からのコードが無事に穴から外に出たので、新しいピンジャックを取り付けます。
ハンダと半田ゴテは、息子が夏休みの自由研究でラジオを作ったときに使ったものです。息子は手先が器用で、難しいラジオをパパッと組み立ててしまいます。

で、私も頑張ってハンダ付けをしましたが・・・息子より下手です。

一応ハンダ付けが出来たので、ピンジャックのカバーを付けてピンジャックの取り付けは完了。

穴周りとコードの処理をもうちょっと考えて、ピンジャックがブラブラしないようにしたいですね。コードが穴のエッジに擦れる状態だと、トラブルの元ですからね。
さてこれで、無事にCM-1がギター本体に取り付けられたことになります。
で、ついでにですが、弦の交換もしてしまいます。
その前に、弦高調整の時にチェックし忘れていた項目がありましたので、この場をお借りしてやりたいと思います。
サンドペーパーでシャカシャカと削ったサドルですが、その後、サドルの底面が『均等に削れているかどうか』を確認する方法がわかりました。
下の画像を見てください。

削ったサドルを、平らな定規などに密着させて光に当てます。すると、平らに削れていない場合、隙間ができて光がもれて見えるんです。その場合は、再度しっかりとサンドペーパーで平らになるように削らなければなりません。
しかし、私の削ったサドルは、光がもれていませんね。良かったです、どうやら底面は均等に削られていたようです。
サドルは、弦の振動をギターの表板に伝えるとても大切な部分になります。もし底面が均等ではなく、例えば高音弦の方に隙間が空いていると、当然、高音弦の振動をギター本体に伝えることは出来ませんね。そうすると、音のバランスの悪いギターになってしまいます。
サドルは、均等に平らな状態でギターのブリッジに『密着』している必要があるんですね。
ただ、私のAPX700は、前回の弦高調整のあと1弦~6弦のバランスがとても良くなっていたので。たぶんサドルの底面に問題は無いだろうとは思っていました。が、実際に確認できて安心しました。
さて、弦はお約束通り、ライトゲージよりも細いマーチン『CUSTOM LIGHT』です。

太さは、1弦・・・0.011インチ 6弦・・・0.052インチ
11-52(イチイチゴーニイ)といえば、エレキの弦でも使われる太さのセットです。
マーチンの弦は、確かもう1段階細いゲージがあると思いましたが。まぁ、音的には11-52ぐらいが限界だと思います。これ以上細いと、アコギの音がしませんね、多分。
ただ、まだアコギを弾き始めたばかりの人は、もっと細い弦でも良いと思います。弾きやすいが一番です。
さて、弦を張るところは省略しまして・・・APX700にカスタムライトの細い弦が張られました。
気になる弦高はどうなったでしょうか?
1弦・・・<1.5mm> 6弦・・・<2.2mm>
出ました!もう、アコギとしては限界の高さですね。
やはり、ゲージが細くなった分、ネックの力の方が強くて反りが軽く、弦高が低くなりましたね。
前回の測定から、<0.2mm>ずつ低くなったのですから、弦のゲージによる弦高の変化は侮れません。追加でサドルをあと<0.1mm>削るか迷いましたけど・・・削らなくて良かった~。
細い弦・ギリギリの弦高のお陰で、何と!APX700は、エレキも含め私が持っているギターの中で一番弾きやすいギターになってしまいました。
この弾きやすさは病み付きで、楽しくてズ~ッと弾き続けられちゃいます。ホントに、楽しい!
ただし!この細い弦と弦高では、音は一気にパワーが無くなり、高音弦は圧倒的に響かなくなりました。
当然と言えば当然なのですが、もしこのギターがエレアコではなくて、アコースティックギターだったら、この音ではとても演奏する気になれません。
これは、当初の目的が『バンドのライブで使う』ことだったので、弾きやすさが最優先。音が犠牲になるのは仕方がありません。
この辺りは、エフェクトやアンプによってフォローしていくしかありませんね。
さて、CM-1の話に戻ります。
CM-1は、電池ボックスに繋がないと音が出ませんので、電池ボックスを何かに固定しなければなりません。あんな重たいものをブラブラとさせておく訳にはいきませんからね。
という訳で、APX700用に買ったストラップにCM-1の電池ボックスを付けることにしました。

まだ仮止めなので、ビニールテープで固定していますが、もう少し固定の方法を考えたいと思います。
で、無事にサウンドホールにカバーを取り付けることも出来ました。

ちなみにストラップは、SCANDALの『MAMI』ちゃんと同じ・・・いやいや『スティーヴィー・レイ・ヴォーン』と同じ音符ストラップです!
さてこれで、APX700にCM-1を取り付ける作業が終わりました。あともう少し調整作業をしたのですが。とりあえずは、これで完成ということにします。
で、肝心のピエゾとCM-1をミックスさせた音ですが。今日はこれで力尽きましたので、また後日にさせて下さい。
☆関連記事
・アコギに使えるピックアップの種類
・BOSS AD5
・コムミュージック CM-1
・ヤマハ エレアコギター APX700II BL
・ヤマハ エレアコギター APX700IIにコンデンサーマイクCM-1を付ける!
・ピエゾ+コンデンサーマイクCM-1の音の検証
☆厳選!ギターを始めたばかりの方にお勧めの記事3つ!
厳選1 メロディ演奏にもコード伴奏にも密接な関連があるCメジャースケール。ギターを初めて触った時から上級者になるまでの練習の必須項目!
【Cメジャースケールを練習しよう!~ギターにおけるCメジャースケールの重要性~】
厳選2 ギターで最初に練習するべき曲は教則本には載っていない場合が多いんです!最初にどんな曲を弾くべきか?またその判別方法は?
【ギターで最初に挑戦する曲は?~キィの判別と教則本の落とし穴~】
厳選3 sinyaが猛烈プッシュするギターの新しい練習方法!いずれは、この練習がギターリストにとっての当たり前になると本気で思っています。ギターの全てが詰まった画期的な練習です!
【ギターリストの新しい練習方法~二胡譜の活用~】


【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!
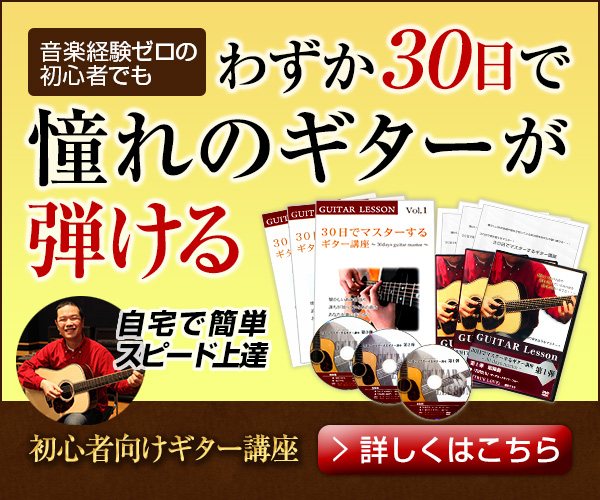

さて、弦高を下げたことにより、スゴク弾きやすくなったAPX700Ⅱですが、まだ調整は終わっていません。
次は、コンデンサーマイク『CM-1』を取り付ける作業になります。
CM-1については、記事【コムミュージック CM-1】に詳しくい書きましたので、参照して下さい。
確かに、APX700は、もともと付いているピエゾタイプのピックアップだけでもなかなか良い音がします。そのままで良いような気もしますし。でも、物足りない感じもする。
もっと『空気感』を足すことが出来たら、迫力のあるサウンドが得られるような気はしました。
CM-1の取り付けに関しては、とても簡単です。CM-1と一体化したクリップを、ギター本体の『力木』につけるだけです。ただ、あとに書くように、CM-1を取り付けるのには『ある程度の覚悟』が必要です。
なので、本当にCM-1を付ける事によって音は向上するのか?
そこをまず確かめる必要があります。始めはCM-1を『仮に』付けてみて、音がどんな風に変わるのかのチェックです。
で、CM-1を付ける為には、弦が邪魔です。なので、やはり弦高調整の時のようにブリッジピンを抜いて弦を外し、作業をしやすいようにします。
CM-1を取り付けた状態が下の画像です。

この状態から、弦を張って音を出してみました。
やはり、ピエゾ+CM-1の音は、空気感が出て迫力があってGOOD!です。
ピエゾだけで音を鳴らしていた時には、これで良いかもしれないと思いましたが・・・CM-1と一緒に鳴らすと、全然違いますね。この迫力のサウンドは、特にロックを弾くと楽しくて止まらなくなります。
という訳で、本格的にCM-1を取り付けることに決定しました。
そこで、まず問題が1つ。
また上の画像を見てください。CM-1から出ているコードが、サウンドホールからだらしなくビロ~ンと出ていますよね。これでは、ピッキングの邪魔だし、見た目も悪い。さらにこれでは、ハウリング防止の為のサウンドホールカバーが付けられないんです。
そこで、コードの取り回しの仕方も考えなければなりません。
APX700は、エンドピン(ギターの一番下にあるピンで、本来はストラップを付けるためのもの)にピエゾピックアップのコードを繋げるようになっています。で、やはりコード類は近い場所にあった方が扱いやすく、トラブルも少ないのではないかと思い、CM-1のコードもエンドピンの近くから出したい。
要は、CM-1のコードを、ギター本体の中を通して、一番下の『エンドピンの横から出す』ということです。
そして『エンドピンの横から出す』為には、コードを出す為の『穴』を開けなければならない、ということなんです。
ハイ、そこで登場するのがこれ。

ギターの調整には、似つかわしくない道具ですね~。これは、バイクを改造する時に散々使ったドリルです。
実はこれが、上で書いた『ある程度の覚悟』という訳です。
ギターに穴を開けなければならないので、CM-1を付ける事によって音質が向上するという確証が必要だったんですね。
もうその確証は得ましたので、作業を進めていきます。
CM-1のコードの太さは2mm。ドリルの刃の直径を、一回り大きい3.5mmにしました。
ドライバーで、ギター本体にガイドとなるパンチを打ちます。ギター本体が振動しないように慎重に。
そして、ドリルのトリガーを微妙に操作して、少しずつ少しずつドリルを回転させました。バイクの改造とは大違いです。
ドリルをゆっくり回していきましたが、穴は簡単に開きました。幸い、他の場所を傷つけることなくキレイに開けることが出来ました。

さぁ、もうこうなったら後戻りは出来ません。ズンズン作業を進めます。
コードを通す為の穴が開きましたので、コードを通します。
もともとCM-1のコードは非常に長かったので、短くしたいこともあり、バッチリ30cmほどコードを切ってしまいました。
当然、電池ボックスに繋げる為のピンジャックも一緒に取れてしまいますので、新たにピンジャックを購入し、後で取り付ける作戦です。

ここで問題が!
CM-1をギターの力木にクリップで固定するまでは良かったのですが。そこから、コードをギターの一番下まで通そうと、サウンドホールに手を入れたら・・・手が入らない!
APX700のサウンドホールは、独特の楕円形をしています。で、かなり一般的なサウンドホールよりも小さいんですね。私の手では、ボディの半分くらいまでしか手が入らない・・・。とても、穴を開けた一番下までは届きません。
あ~あ、手の小さい妻や息子が帰って来るまで待てないし・・・。
そこで思いつきました。『釣り込み作戦』です。
先ほど切ったコードのあまりを、ギター本体の『外側から』開けた穴に通します。そのコードをギター本体に少しずつ入れていき、CM-1から出ているコードを迎えに行かせます。外側から入れたコードとCM-1から出ているコードをハンダで簡単にくっ付けて、外側から入れたコードを今度はたぐり寄せてきます。すると・・・

ハイ、CM-1のコードが見事に釣れて、ギターの外に出てきました!
この『釣り込み作戦』は、ギターのサウンドに1mmも影響を与えないので、忘れてくださって結構です。
さて、CM-1からのコードが無事に穴から外に出たので、新しいピンジャックを取り付けます。
ハンダと半田ゴテは、息子が夏休みの自由研究でラジオを作ったときに使ったものです。息子は手先が器用で、難しいラジオをパパッと組み立ててしまいます。

で、私も頑張ってハンダ付けをしましたが・・・息子より下手です。

一応ハンダ付けが出来たので、ピンジャックのカバーを付けてピンジャックの取り付けは完了。

穴周りとコードの処理をもうちょっと考えて、ピンジャックがブラブラしないようにしたいですね。コードが穴のエッジに擦れる状態だと、トラブルの元ですからね。
さてこれで、無事にCM-1がギター本体に取り付けられたことになります。
で、ついでにですが、弦の交換もしてしまいます。
その前に、弦高調整の時にチェックし忘れていた項目がありましたので、この場をお借りしてやりたいと思います。
サンドペーパーでシャカシャカと削ったサドルですが、その後、サドルの底面が『均等に削れているかどうか』を確認する方法がわかりました。
下の画像を見てください。

削ったサドルを、平らな定規などに密着させて光に当てます。すると、平らに削れていない場合、隙間ができて光がもれて見えるんです。その場合は、再度しっかりとサンドペーパーで平らになるように削らなければなりません。
しかし、私の削ったサドルは、光がもれていませんね。良かったです、どうやら底面は均等に削られていたようです。
サドルは、弦の振動をギターの表板に伝えるとても大切な部分になります。もし底面が均等ではなく、例えば高音弦の方に隙間が空いていると、当然、高音弦の振動をギター本体に伝えることは出来ませんね。そうすると、音のバランスの悪いギターになってしまいます。
サドルは、均等に平らな状態でギターのブリッジに『密着』している必要があるんですね。
ただ、私のAPX700は、前回の弦高調整のあと1弦~6弦のバランスがとても良くなっていたので。たぶんサドルの底面に問題は無いだろうとは思っていました。が、実際に確認できて安心しました。
さて、弦はお約束通り、ライトゲージよりも細いマーチン『CUSTOM LIGHT』です。

太さは、1弦・・・0.011インチ 6弦・・・0.052インチ
11-52(イチイチゴーニイ)といえば、エレキの弦でも使われる太さのセットです。
マーチンの弦は、確かもう1段階細いゲージがあると思いましたが。まぁ、音的には11-52ぐらいが限界だと思います。これ以上細いと、アコギの音がしませんね、多分。
ただ、まだアコギを弾き始めたばかりの人は、もっと細い弦でも良いと思います。弾きやすいが一番です。
さて、弦を張るところは省略しまして・・・APX700にカスタムライトの細い弦が張られました。
気になる弦高はどうなったでしょうか?
1弦・・・<1.5mm> 6弦・・・<2.2mm>
出ました!もう、アコギとしては限界の高さですね。
やはり、ゲージが細くなった分、ネックの力の方が強くて反りが軽く、弦高が低くなりましたね。
前回の測定から、<0.2mm>ずつ低くなったのですから、弦のゲージによる弦高の変化は侮れません。追加でサドルをあと<0.1mm>削るか迷いましたけど・・・削らなくて良かった~。
細い弦・ギリギリの弦高のお陰で、何と!APX700は、エレキも含め私が持っているギターの中で一番弾きやすいギターになってしまいました。
この弾きやすさは病み付きで、楽しくてズ~ッと弾き続けられちゃいます。ホントに、楽しい!
ただし!この細い弦と弦高では、音は一気にパワーが無くなり、高音弦は圧倒的に響かなくなりました。
当然と言えば当然なのですが、もしこのギターがエレアコではなくて、アコースティックギターだったら、この音ではとても演奏する気になれません。
これは、当初の目的が『バンドのライブで使う』ことだったので、弾きやすさが最優先。音が犠牲になるのは仕方がありません。
この辺りは、エフェクトやアンプによってフォローしていくしかありませんね。
さて、CM-1の話に戻ります。
CM-1は、電池ボックスに繋がないと音が出ませんので、電池ボックスを何かに固定しなければなりません。あんな重たいものをブラブラとさせておく訳にはいきませんからね。
という訳で、APX700用に買ったストラップにCM-1の電池ボックスを付けることにしました。

まだ仮止めなので、ビニールテープで固定していますが、もう少し固定の方法を考えたいと思います。
で、無事にサウンドホールにカバーを取り付けることも出来ました。

ちなみにストラップは、SCANDALの『MAMI』ちゃんと同じ・・・いやいや『スティーヴィー・レイ・ヴォーン』と同じ音符ストラップです!
さてこれで、APX700にCM-1を取り付ける作業が終わりました。あともう少し調整作業をしたのですが。とりあえずは、これで完成ということにします。
で、肝心のピエゾとCM-1をミックスさせた音ですが。今日はこれで力尽きましたので、また後日にさせて下さい。
☆関連記事
・アコギに使えるピックアップの種類
・BOSS AD5
・コムミュージック CM-1
・ヤマハ エレアコギター APX700II BL
・ヤマハ エレアコギター APX700IIにコンデンサーマイクCM-1を付ける!
・ピエゾ+コンデンサーマイクCM-1の音の検証
☆厳選!ギターを始めたばかりの方にお勧めの記事3つ!
厳選1 メロディ演奏にもコード伴奏にも密接な関連があるCメジャースケール。ギターを初めて触った時から上級者になるまでの練習の必須項目!
【Cメジャースケールを練習しよう!~ギターにおけるCメジャースケールの重要性~】
厳選2 ギターで最初に練習するべき曲は教則本には載っていない場合が多いんです!最初にどんな曲を弾くべきか?またその判別方法は?
【ギターで最初に挑戦する曲は?~キィの判別と教則本の落とし穴~】
厳選3 sinyaが猛烈プッシュするギターの新しい練習方法!いずれは、この練習がギターリストにとっての当たり前になると本気で思っています。ギターの全てが詰まった画期的な練習です!
【ギターリストの新しい練習方法~二胡譜の活用~】


【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!
2013年02月08日
テレキャスのネック調整
⇒【sinyaが開発!弾く脳トレ!よなおしギター】
以前の記事【ギターの自宅練習に最適なアンプ!~PLAYTECH JAMMER Jr. FX~】で、とにかく暇があったらギターに触れるように、リビングにもギターとミニアンプを設置したことを書きました。
お陰で、本当に暇さえあればギターに触っている状態になったのですが。今日、いつものようにリビングでギターを弾いていましたら、妙に弾き難い。弦高がいつの間にかスゴク高くなっている訳です。
『これはもしかして』
と思い、ネックを調べましたら、見事な『順反り』。
ギターの弦による張力は、普通にチューニングした状態だと60キロぐらいあると言われています。もちろん、アコギかエレキでも違いますし、弦のゲージによっても差はありますが・・・。
もし、張力が60キロあるとするならば、弦を張った状態のギターは、常にヘッドの上に大人が1人乗っかっている状態にあるということ。頭に人が乗ったら、人間だって腰が曲がる訳で。そりゃあ、ほとんどが木で出来ているギターにとっては、文字通り荷が重い訳です。
で、ネックの反りを防止するには、『1.弾かない時は弦を緩める』ことと『2.気温・湿度の管理』が言われます。
今の季節、我が家のリビングは、下手をすると湿度20%を切ってきます。これは、人間にも良くない数値ですよね。当然、ギターにも良くない訳です。
ギターは、材質が木なので、気温の変化よりも湿度の変化の方がダメージが大きいようで。ここ数日、雨が降っていましたので、湿度がある程度上がっていたところに、今日は快晴、空っ風が吹いてとても乾燥したんです。
我がギターは、この急激な湿度変化に付いていけなかったようです。
気温・湿度の管理については、あまり神経質になることも無いと思います。基本、人間にとって快適な数値なら問題ないと思いますので。
ただ、日本は気温も湿度も変化の激しい国ですね。梅雨時の前後、冬の乾燥する時期の前後の、環境が急激に変化する時期は気をつけましょう。
プラス、正確な温度計・湿度計を購入し、常に数値を把握すること。そして、やはり管理は個室の方がしやすいですね。
という訳で。湿度の変化を管理し難いリビングに置いた、弦を張りっぱなし状態の私のギターは、過酷な環境下で頑張っていたことになります。が、ここにきて、とうとう耐えかねてしまったようです。
早速、ネックの反りを治してあげましょう。
まず、ネックの『順反り』とはどういう状態なのかを図解します。

もの凄く極端な図ですが、順反りすると弦高が高くなる理屈が良く分かりますね。
で、実際の私のギターは、下の画像のような反りでした。
1弦側

6弦側

少し分かり難いですが、このようにヘッドの方から覗いて見ると、ネックの反りが確認できます。
さて、これを治す方法ですが。その前に、素人レベルで治せる反りの程度は、とても限られていると、ある意味『諦め』も肝心です。私のこのギターの反り程度でも『かなり反っている』状態だと言えます。これ以上の反りの場合は、やはり専門の技術を持った人に見てもらいましょう。
で、ギターのネックの中には、ほぼ確実に『トラスロッド』といわれる長いボルトが入っています。このボルトを締めたり緩めたりすることでネックの反りを修正していきます。
トラスロッドを調整する方法は、メーカーやギターの種類によって様々です。
私のこのギターは、ネックとボディを4つのネジで留める、いわゆる『デタッチャブル・ネック』といわれる構造で。さらに、トラスロッドを調整するための『調整口』が、ボディに埋まっているタイプです。まぁ、ネック調整には一番手間が掛かるタイプと言えます。

ネック調整のやり方を手順を追って見ていきましょう。
まず、弦を外します。このタイプのギターは、弦を緩めるとペグ部分からスポッと弦が抜けてくれます。弦を切らないで外せるので、ネック調整が終わった後、このまま同じ弦を張ることが可能です。

ボディの裏にある、ネックとボディを留める4つのネジを外します。

ネックが取れて、プラスの形をしたトラスロッドの頭が見えました。

ギターの種類によっては、トラスロッドを六角レンチで調整するものもありますが、このギターは、ドライバーで調整できます。
『順反り』のネックを治す場合は、このトラスロッドを『時計回りに』回します。
回す時の注意は、一気に回さないこと。多くても、時計の長針でいうところの『15分ずつ』ぐらい。私は怖がりなので、今回は『5分ずつ』ゆっくりと慎重に回しました。
反りの状態がヒドかったので、なかなか真っ直ぐになってくれません。結構、硬くなるまで締め、やっと少しまともになった感じになりましたが。まだ少し反った状態です。
もう少し締めていきたいところですが、ネックが『ミシミシ』と鳴ったので、これ以上は危険と判断し調整を終了することにしました。
ネック調整が終わったら、ボディとネックをネジで留めて、弦を張って終わりです。
完全には治っていませんが、まぁ、これが精一杯ですね。
1弦側

6弦側

1弦側と6弦側で、反りの状態が違うので、恐らくネックが『ねじれている』状態だと思います。こうなると、素人レベルでは治すのが難しいです。というより、私には無理です。
このギターは、楽器店にてデザインが気に入って購入したものです。確か、3万円ほどだったと思います。
で、知人がギターを弾きたいというので、貸していました。その知人は、しばらくすると弾かなくなり、何年も置きっ放しになっていたようです。帰ってきた時には、だいぶ痛んでいました。
その後、簡単なリペアに出して、何とか弾ける状態にはなりましたが。一度痛んでしまったものは、なかなか完全復活とまではいきませんね。
『デタッチャブル・ネック』の場合、ネック交換が簡単なので、ネック自体を変えてしまうのも手ですが。まぁ、リビング練習用には問題なさそうなので、管理に気をつけて、もう少し様子を見てみます。

やはり、定期的にちゃんと弾いてあげることが、ギターにとって一番の幸せですね。
☆厳選!ギターを始めたばかりの方にお勧めの記事3つ!
厳選1 メロディ演奏にもコード伴奏にも密接な関連があるCメジャースケール。ギターを初めて触った時から上級者になるまでの練習の必須項目!
【Cメジャースケールを練習しよう!~ギターにおけるCメジャースケールの重要性~】
厳選2 ギターで最初に練習するべき曲は教則本には載っていない場合が多いんです!最初にどんな曲を弾くべきか?またその判別方法は?
【ギターで最初に挑戦する曲は?~キィの判別と教則本の落とし穴~】
厳選3 sinyaが猛烈プッシュするギターの新しい練習方法!いずれは、この練習がギターリストにとっての当たり前になると本気で思っています。ギターの全てが詰まった画期的な練習です!
【ギターリストの新しい練習方法~二胡譜の活用~】


【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!
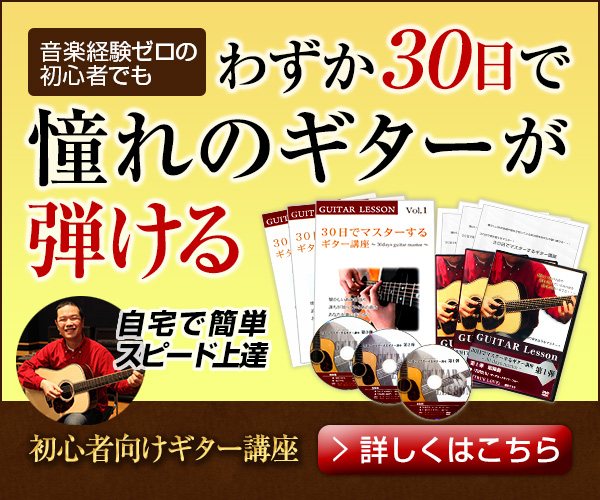

以前の記事【ギターの自宅練習に最適なアンプ!~PLAYTECH JAMMER Jr. FX~】で、とにかく暇があったらギターに触れるように、リビングにもギターとミニアンプを設置したことを書きました。
お陰で、本当に暇さえあればギターに触っている状態になったのですが。今日、いつものようにリビングでギターを弾いていましたら、妙に弾き難い。弦高がいつの間にかスゴク高くなっている訳です。
『これはもしかして』
と思い、ネックを調べましたら、見事な『順反り』。
ギターの弦による張力は、普通にチューニングした状態だと60キロぐらいあると言われています。もちろん、アコギかエレキでも違いますし、弦のゲージによっても差はありますが・・・。
もし、張力が60キロあるとするならば、弦を張った状態のギターは、常にヘッドの上に大人が1人乗っかっている状態にあるということ。頭に人が乗ったら、人間だって腰が曲がる訳で。そりゃあ、ほとんどが木で出来ているギターにとっては、文字通り荷が重い訳です。
で、ネックの反りを防止するには、『1.弾かない時は弦を緩める』ことと『2.気温・湿度の管理』が言われます。
今の季節、我が家のリビングは、下手をすると湿度20%を切ってきます。これは、人間にも良くない数値ですよね。当然、ギターにも良くない訳です。
ギターは、材質が木なので、気温の変化よりも湿度の変化の方がダメージが大きいようで。ここ数日、雨が降っていましたので、湿度がある程度上がっていたところに、今日は快晴、空っ風が吹いてとても乾燥したんです。
我がギターは、この急激な湿度変化に付いていけなかったようです。
気温・湿度の管理については、あまり神経質になることも無いと思います。基本、人間にとって快適な数値なら問題ないと思いますので。
ただ、日本は気温も湿度も変化の激しい国ですね。梅雨時の前後、冬の乾燥する時期の前後の、環境が急激に変化する時期は気をつけましょう。
プラス、正確な温度計・湿度計を購入し、常に数値を把握すること。そして、やはり管理は個室の方がしやすいですね。
という訳で。湿度の変化を管理し難いリビングに置いた、弦を張りっぱなし状態の私のギターは、過酷な環境下で頑張っていたことになります。が、ここにきて、とうとう耐えかねてしまったようです。
早速、ネックの反りを治してあげましょう。
まず、ネックの『順反り』とはどういう状態なのかを図解します。
もの凄く極端な図ですが、順反りすると弦高が高くなる理屈が良く分かりますね。
で、実際の私のギターは、下の画像のような反りでした。
1弦側

6弦側

少し分かり難いですが、このようにヘッドの方から覗いて見ると、ネックの反りが確認できます。
さて、これを治す方法ですが。その前に、素人レベルで治せる反りの程度は、とても限られていると、ある意味『諦め』も肝心です。私のこのギターの反り程度でも『かなり反っている』状態だと言えます。これ以上の反りの場合は、やはり専門の技術を持った人に見てもらいましょう。
で、ギターのネックの中には、ほぼ確実に『トラスロッド』といわれる長いボルトが入っています。このボルトを締めたり緩めたりすることでネックの反りを修正していきます。
トラスロッドを調整する方法は、メーカーやギターの種類によって様々です。
私のこのギターは、ネックとボディを4つのネジで留める、いわゆる『デタッチャブル・ネック』といわれる構造で。さらに、トラスロッドを調整するための『調整口』が、ボディに埋まっているタイプです。まぁ、ネック調整には一番手間が掛かるタイプと言えます。

ネック調整のやり方を手順を追って見ていきましょう。
まず、弦を外します。このタイプのギターは、弦を緩めるとペグ部分からスポッと弦が抜けてくれます。弦を切らないで外せるので、ネック調整が終わった後、このまま同じ弦を張ることが可能です。

ボディの裏にある、ネックとボディを留める4つのネジを外します。

ネックが取れて、プラスの形をしたトラスロッドの頭が見えました。

ギターの種類によっては、トラスロッドを六角レンチで調整するものもありますが、このギターは、ドライバーで調整できます。
『順反り』のネックを治す場合は、このトラスロッドを『時計回りに』回します。
回す時の注意は、一気に回さないこと。多くても、時計の長針でいうところの『15分ずつ』ぐらい。私は怖がりなので、今回は『5分ずつ』ゆっくりと慎重に回しました。
反りの状態がヒドかったので、なかなか真っ直ぐになってくれません。結構、硬くなるまで締め、やっと少しまともになった感じになりましたが。まだ少し反った状態です。
もう少し締めていきたいところですが、ネックが『ミシミシ』と鳴ったので、これ以上は危険と判断し調整を終了することにしました。
ネック調整が終わったら、ボディとネックをネジで留めて、弦を張って終わりです。
完全には治っていませんが、まぁ、これが精一杯ですね。
1弦側

6弦側

1弦側と6弦側で、反りの状態が違うので、恐らくネックが『ねじれている』状態だと思います。こうなると、素人レベルでは治すのが難しいです。というより、私には無理です。
このギターは、楽器店にてデザインが気に入って購入したものです。確か、3万円ほどだったと思います。
で、知人がギターを弾きたいというので、貸していました。その知人は、しばらくすると弾かなくなり、何年も置きっ放しになっていたようです。帰ってきた時には、だいぶ痛んでいました。
その後、簡単なリペアに出して、何とか弾ける状態にはなりましたが。一度痛んでしまったものは、なかなか完全復活とまではいきませんね。
『デタッチャブル・ネック』の場合、ネック交換が簡単なので、ネック自体を変えてしまうのも手ですが。まぁ、リビング練習用には問題なさそうなので、管理に気をつけて、もう少し様子を見てみます。

やはり、定期的にちゃんと弾いてあげることが、ギターにとって一番の幸せですね。
☆厳選!ギターを始めたばかりの方にお勧めの記事3つ!
厳選1 メロディ演奏にもコード伴奏にも密接な関連があるCメジャースケール。ギターを初めて触った時から上級者になるまでの練習の必須項目!
【Cメジャースケールを練習しよう!~ギターにおけるCメジャースケールの重要性~】
厳選2 ギターで最初に練習するべき曲は教則本には載っていない場合が多いんです!最初にどんな曲を弾くべきか?またその判別方法は?
【ギターで最初に挑戦する曲は?~キィの判別と教則本の落とし穴~】
厳選3 sinyaが猛烈プッシュするギターの新しい練習方法!いずれは、この練習がギターリストにとっての当たり前になると本気で思っています。ギターの全てが詰まった画期的な練習です!
【ギターリストの新しい練習方法~二胡譜の活用~】


【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!
2013年02月04日
ヤマハ エレアコギター APX700II の弦高調整の弾き心地
⇒【sinyaが開発!弾く脳トレ!よなおしギター】
少し問題もありましたが、何とか弦高調整が終了したAPX700。
調整後の弾き心地を、私感全開で書いてみます。
その前に、なぜAPX700の弦高を低くしようと思ったかを簡単に説明しますと、最終的にはバンドのライブで使いたいからです。
仮に調整をしなくても、例えば自宅でのレコーディングやレッスンでの使用なら全く問題ない程度の弦高でした。
ただ、ライブは話が違いますね。
ライブでは、テクニック的には練習の半分も表現することが出来ないと思っています。あんなに弾きやすいエレキギターでさえそんなですから・・・。しかも、私はバンドのライブではアコギを弾いた経験が無いんです。
そんなことを複合的に考えますと、ライブで使うエレアコは『徹底的に弾きやすい』必要があります。
という訳で、私は、弦高調整の決行にいたりました。
ただ、弦高を低くすることで弾きやすさと引き換えに音色を犠牲にする場合もあります。闇雲に弦を低くすれば良いという訳でもないと思いますので、ご注意下さい。
前置きはこれくらいにして・・・
調整後のAPX700の弾き心地は、ズバリ!最高です。
たった<0.2mm>弦高が低くなっただけで、ここまで変わるのか!と、本当に驚きです。
幸い、(弦高が低くなり過ぎて)弦がフレットに触れてノイズが出ることも無く、調整は成功したようです。
ただ、あと<0.1mm>ほど低くしても良いかもしれないと思いました。
今の状態でも十分に弾きやすいのですが、ライブで使用することを考えると、もうちょっとエレキギターに近づけても良いかな~と。(「ならエレキを使えばいいじゃん」というご意見は当然ですが・・・ちょっと横に置かさせていただきます。)
あと<0.1mm>低くするかしないかについては、弦を替えてから考えてみます。
というのも、APX700に今張ってある弦は、買った時のままです。恐らく、ライトゲージだと思います。で、私はライトゲージよりも細い弦を張って使う予定でいます。という事は、今の状態よりも『弦の張力が弱くなる=さらに弦高が低くなる』可能性がありますので。今のところはあと<0.1mm>弦高を低くするのは頑張って我慢します。
まぁ、最初に奇跡的に上手くいったからと調子に乗って欲を出すと、だいたい失敗しますからね。
という訳で。弦高に関しては、取りあえず一回の調整でストップです。で、最終的に全ての調整が終わった後にまた考えてみます。
さて、たった<0.2mm>弦高が低くなっただけで弾きやすさが激変したAPX700ですが、それ以外にも変化がありました。
音が良くなった感じがするんです。正確に言うと『音のバランスが良くなった』んです。
先ほども書いたように、弦高を低くすると音色を犠牲にする場合もあります。それを覚悟していたので、この音の変化は驚きです。
で、少し調べてみました。
一般的に、弦高を低くすると、1弦2弦(プレーン弦)の音は小さく痩せていくようです。一方、3弦~6弦(巻き弦)の低音弦は弦高に左右されずに音をキープできるので、相対的に太く良い音になっていく傾向があるようです。
ですから、弦高を低く低くしていくと、その内、1弦・2弦の音は低音弦の音に埋もれていってしまって、大切なメロディが聞こえてこなくなるらしいんですね。
という事は、もともと低音が大きく響くボディが大きなギターなどは、弦高の下げすぎに注意ということになります。
逆に考えますと、もともと高音が強調されたような、今流行の小振りのギターなら、ある程度弦高を低くしても大丈夫ということですね。
はい、全然知りませんでした。知らずに、サドルをガリガリと削っていました。
弦高を低くすると音やせするのは想像できましたが、プレーン弦と巻き弦で反応に差が出るとは・・・勉強不足ですね。
では、なぜ私のAPX700は調整後にバランスが良くなったのか?
このギターを買った時のブログにも書きましたが、YAMAHAのギターはもともとキラキラと綺麗な音がするんです。これは、メーカーの特徴と言って良いと思います。
音がキラキラしているという事は、高音が強調されているということですね。そうです、APX700も、しっかりYAMAHAの特徴であるキラキラした音が始めから出てました。これは、この小振りなボディも影響していると思いますが、確かに、高音が良く聞こえるギターでした。
で、今回の弦高調整のお陰で、相対的に『低音が上がり高音が下がった』訳です。
YAMAHA的にはバランスが崩れた形になるかもしれませんが、ギター的には、低音~高音までとてもバランスの良い音を奏でるギターとなった訳です。
知らずにやったこととはいえ、弦高を低くしたことの副作用が、良い方向に働いたことになります。
弦高が低くなった上、音のバランスが良くなったAPX700。もう、弾くのが楽しくてズッと弾いていたくなります。
もちろん、音色・音圧とも、アストリアスの方が圧倒的に良い訳ですが。自分で調整したギターとは、これほどまでに愛着が湧くものかと。APX700が、もう可愛くて仕方ないんです。
この『愛着』は、自分でギターを調整することによって得られるものの中で、スゴク大切な要素であるのは間違いないでしょう。
もちろん、弾きやすさや音質の変化も大切です。それを目的に調整をすることがほとんどだと思います。が、それらの要素との相乗効果で、買ったばかりのギターにここまで『愛着』が湧くとは思いませんでした。嬉しい誤算です。
ギターの調整って、やり始めると止まらなくなるようですが、その理由が良く分かりました。
まぁ、それでもあまり調整ばかりに時間と頭をとられる訳にはいかないので、調整作業の予定変更はしないつもりです。
なので、次はコンデンサーマイク『CM-1』の取り付けに挑戦です。
近日中にブログに作業状況をアップしたいと思います。
☆関連記事
・ヤマハ エレアコギター APX700II
・ヤマハ エレアコギター APX700II の弦高調整
・ヤマハ エレアコギター APX700II の弦高調整2
・ヤマハ エレアコギター APX700II の弦高調整後の弾き心地
・ヤマハ エレアコギター APX700IIにコンデンサーマイクCM-1を付ける!
・ピエゾ+コンデンサーマイクCM-1の音の検証
☆厳選!ギターを始めたばかりの方にお勧めの記事3つ!
厳選1 メロディ演奏にもコード伴奏にも密接な関連があるCメジャースケール。ギターを初めて触った時から上級者になるまでの練習の必須項目!
【Cメジャースケールを練習しよう!~ギターにおけるCメジャースケールの重要性~】
厳選2 ギターで最初に練習するべき曲は教則本には載っていない場合が多いんです!最初にどんな曲を弾くべきか?またその判別方法は?
【ギターで最初に挑戦する曲は?~キィの判別と教則本の落とし穴~】
厳選3 sinyaが猛烈プッシュするギターの新しい練習方法!いずれは、この練習がギターリストにとっての当たり前になると本気で思っています。ギターの全てが詰まった画期的な練習です!
【ギターリストの新しい練習方法~二胡譜の活用~】


【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!
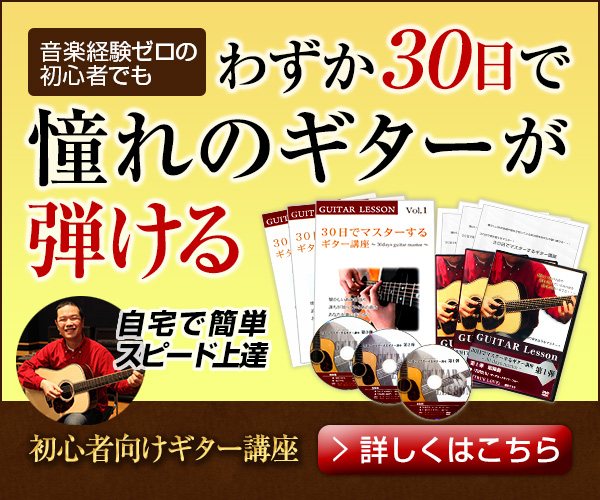

少し問題もありましたが、何とか弦高調整が終了したAPX700。
調整後の弾き心地を、私感全開で書いてみます。
その前に、なぜAPX700の弦高を低くしようと思ったかを簡単に説明しますと、最終的にはバンドのライブで使いたいからです。
仮に調整をしなくても、例えば自宅でのレコーディングやレッスンでの使用なら全く問題ない程度の弦高でした。
ただ、ライブは話が違いますね。
ライブでは、テクニック的には練習の半分も表現することが出来ないと思っています。あんなに弾きやすいエレキギターでさえそんなですから・・・。しかも、私はバンドのライブではアコギを弾いた経験が無いんです。
そんなことを複合的に考えますと、ライブで使うエレアコは『徹底的に弾きやすい』必要があります。
という訳で、私は、弦高調整の決行にいたりました。
ただ、弦高を低くすることで弾きやすさと引き換えに音色を犠牲にする場合もあります。闇雲に弦を低くすれば良いという訳でもないと思いますので、ご注意下さい。
前置きはこれくらいにして・・・
調整後のAPX700の弾き心地は、ズバリ!最高です。
たった<0.2mm>弦高が低くなっただけで、ここまで変わるのか!と、本当に驚きです。
幸い、(弦高が低くなり過ぎて)弦がフレットに触れてノイズが出ることも無く、調整は成功したようです。
ただ、あと<0.1mm>ほど低くしても良いかもしれないと思いました。
今の状態でも十分に弾きやすいのですが、ライブで使用することを考えると、もうちょっとエレキギターに近づけても良いかな~と。(「ならエレキを使えばいいじゃん」というご意見は当然ですが・・・ちょっと横に置かさせていただきます。)
あと<0.1mm>低くするかしないかについては、弦を替えてから考えてみます。
というのも、APX700に今張ってある弦は、買った時のままです。恐らく、ライトゲージだと思います。で、私はライトゲージよりも細い弦を張って使う予定でいます。という事は、今の状態よりも『弦の張力が弱くなる=さらに弦高が低くなる』可能性がありますので。今のところはあと<0.1mm>弦高を低くするのは頑張って我慢します。
まぁ、最初に奇跡的に上手くいったからと調子に乗って欲を出すと、だいたい失敗しますからね。
という訳で。弦高に関しては、取りあえず一回の調整でストップです。で、最終的に全ての調整が終わった後にまた考えてみます。
さて、たった<0.2mm>弦高が低くなっただけで弾きやすさが激変したAPX700ですが、それ以外にも変化がありました。
音が良くなった感じがするんです。正確に言うと『音のバランスが良くなった』んです。
先ほども書いたように、弦高を低くすると音色を犠牲にする場合もあります。それを覚悟していたので、この音の変化は驚きです。
で、少し調べてみました。
一般的に、弦高を低くすると、1弦2弦(プレーン弦)の音は小さく痩せていくようです。一方、3弦~6弦(巻き弦)の低音弦は弦高に左右されずに音をキープできるので、相対的に太く良い音になっていく傾向があるようです。
ですから、弦高を低く低くしていくと、その内、1弦・2弦の音は低音弦の音に埋もれていってしまって、大切なメロディが聞こえてこなくなるらしいんですね。
という事は、もともと低音が大きく響くボディが大きなギターなどは、弦高の下げすぎに注意ということになります。
逆に考えますと、もともと高音が強調されたような、今流行の小振りのギターなら、ある程度弦高を低くしても大丈夫ということですね。
はい、全然知りませんでした。知らずに、サドルをガリガリと削っていました。
弦高を低くすると音やせするのは想像できましたが、プレーン弦と巻き弦で反応に差が出るとは・・・勉強不足ですね。
では、なぜ私のAPX700は調整後にバランスが良くなったのか?
このギターを買った時のブログにも書きましたが、YAMAHAのギターはもともとキラキラと綺麗な音がするんです。これは、メーカーの特徴と言って良いと思います。
音がキラキラしているという事は、高音が強調されているということですね。そうです、APX700も、しっかりYAMAHAの特徴であるキラキラした音が始めから出てました。これは、この小振りなボディも影響していると思いますが、確かに、高音が良く聞こえるギターでした。
で、今回の弦高調整のお陰で、相対的に『低音が上がり高音が下がった』訳です。
YAMAHA的にはバランスが崩れた形になるかもしれませんが、ギター的には、低音~高音までとてもバランスの良い音を奏でるギターとなった訳です。
知らずにやったこととはいえ、弦高を低くしたことの副作用が、良い方向に働いたことになります。
弦高が低くなった上、音のバランスが良くなったAPX700。もう、弾くのが楽しくてズッと弾いていたくなります。
もちろん、音色・音圧とも、アストリアスの方が圧倒的に良い訳ですが。自分で調整したギターとは、これほどまでに愛着が湧くものかと。APX700が、もう可愛くて仕方ないんです。
この『愛着』は、自分でギターを調整することによって得られるものの中で、スゴク大切な要素であるのは間違いないでしょう。
もちろん、弾きやすさや音質の変化も大切です。それを目的に調整をすることがほとんどだと思います。が、それらの要素との相乗効果で、買ったばかりのギターにここまで『愛着』が湧くとは思いませんでした。嬉しい誤算です。
ギターの調整って、やり始めると止まらなくなるようですが、その理由が良く分かりました。
まぁ、それでもあまり調整ばかりに時間と頭をとられる訳にはいかないので、調整作業の予定変更はしないつもりです。
なので、次はコンデンサーマイク『CM-1』の取り付けに挑戦です。
近日中にブログに作業状況をアップしたいと思います。
☆関連記事
・ヤマハ エレアコギター APX700II
・ヤマハ エレアコギター APX700II の弦高調整
・ヤマハ エレアコギター APX700II の弦高調整2
・ヤマハ エレアコギター APX700II の弦高調整後の弾き心地
・ヤマハ エレアコギター APX700IIにコンデンサーマイクCM-1を付ける!
・ピエゾ+コンデンサーマイクCM-1の音の検証
☆厳選!ギターを始めたばかりの方にお勧めの記事3つ!
厳選1 メロディ演奏にもコード伴奏にも密接な関連があるCメジャースケール。ギターを初めて触った時から上級者になるまでの練習の必須項目!
【Cメジャースケールを練習しよう!~ギターにおけるCメジャースケールの重要性~】
厳選2 ギターで最初に練習するべき曲は教則本には載っていない場合が多いんです!最初にどんな曲を弾くべきか?またその判別方法は?
【ギターで最初に挑戦する曲は?~キィの判別と教則本の落とし穴~】
厳選3 sinyaが猛烈プッシュするギターの新しい練習方法!いずれは、この練習がギターリストにとっての当たり前になると本気で思っています。ギターの全てが詰まった画期的な練習です!
【ギターリストの新しい練習方法~二胡譜の活用~】


【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!