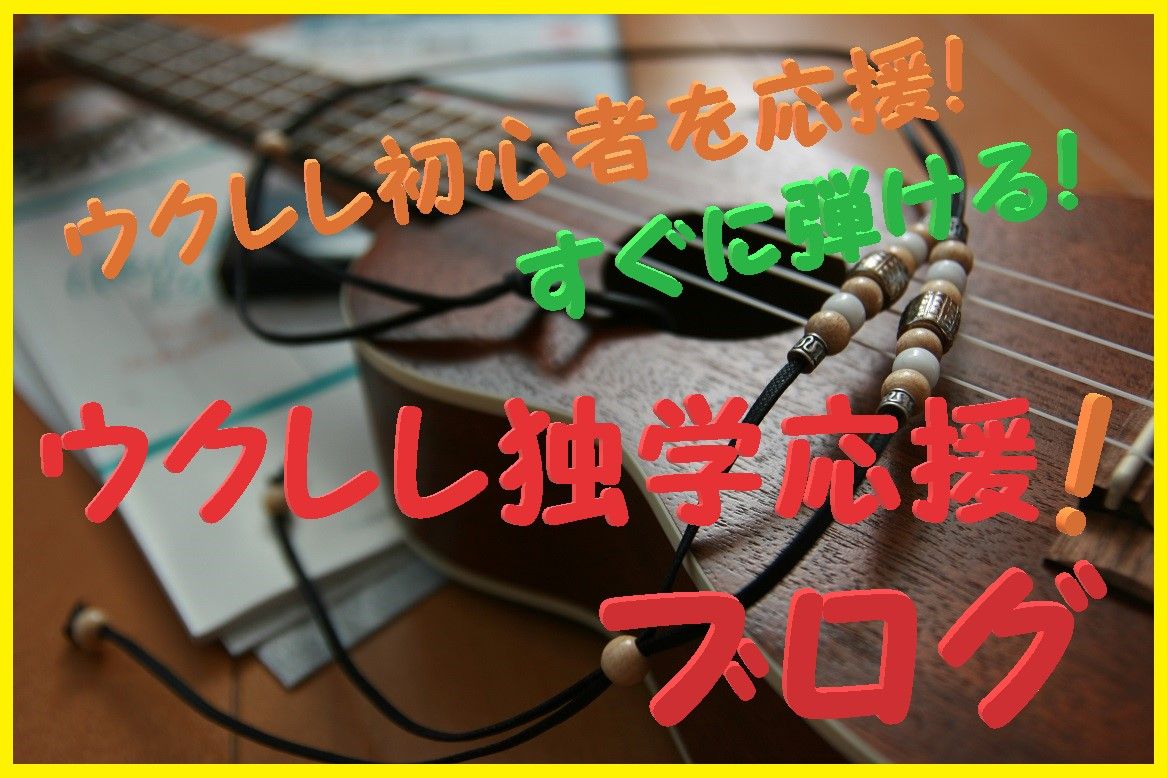2013年02月03日
ヤマハ エレアコギター APX700II の弦高調整 2
⇒【sinyaが開発!弾く脳トレ!よなおしギター】
APX700から外したサドルの底面が、斜めだった件。写真では分かり難かったので、図で説明します。

従来のサドルは、底面が平らです。なので、底面を削る時には、サドルをサンドペーパーに『直角』に当てます。削っている最中にも、時々その『直角』を確認することによって、底面が平らに削られているかどうかの判断をする訳です。
ところが、APX700は図の右のように、サドルの底面が斜めになっていました。これでは、サンドペーパーに『直角』に当てることは出来ません。『直角』に当てることが出来ないということは、平らに削られているかどうかの判断材料を失ってしまうことになります。
とはいえ、いてもたっていられずに始めた作業なので、ここで止めるのも悔しいし、今から新しいサドルを注文して届くまで待てる自信もありません。
で、考えられる案は2つ。
第一案・・・斜めになっている部分を削って平らにしてしまう。
第二案・・・斜めのまま削る。

APX700のサドルの底面が、なぜ斜めになっているのか?その理由は分かりません。ただ、もちろん意味があってのことだと思います。なので、出来れば斜めの状態を保ちたい。
そして、第一案のように斜めの部分をカットしてしまうと、予定の削る量を大幅にオーバーしてしまいます。サドルの底を削る量は、前回の計算では<0.4mm>です。斜めの部分をカットしたら、恐らくその倍は削れてしまいます。
そんなに削ったら、弦高が低くなり過ぎて、音に支障が出てしまうと思います。
という訳で、第二案を決行いたします。
『直角』があてにならない以上、削る前の斜めの角度を保ちながら削る他ありません。
しかし、斜めの角度を正確に保ちながら底面を削る方法が思い浮かばないので、全てを『自分の手の感覚』にゆだねることにしました。
う~ん、職人さんみたいでカッコイイです。もう一度言います、私、アコギの弦高調整は初めてです。
そうと決まりましたので。作業を続行いたします。
前回、手順③までいきましたので、手順④ 削る前のサドルを測定します。
サドルは、真っ白い部品です。そのままでは、どこを基点に測定して良いのか分かりません。なので、計測の基点となる線をマジックで入れます。これは、1弦と6弦の当たる位置の2箇所で良いと思います。が、何となく1弦~6弦の全6箇所に印を付けてしまいました。

この計測基点を元に測ります。

測定の結果、削る前のサドルは以下のような状態でした。
削る前のサドルの寸法
1弦側<6.1mm> 6弦側<8.0mm>
ちなみに測定には『ノギス』を使います。

本尺目盛りと副尺目盛りを組み合わせることにより、最小で<0.05mm>まで読み取ることが出来ます。サドルを削る量は<0.4mm>と、1mm以下を正確に測る必要がありますので。やはり、ノギスを使った方が良いですね。
削る量が<0.4mm>なので、サドルの目標数値は以下のようになります。
1弦側 6.1-0.4 = <5.7mm>
6弦側 8.0-0.4 = <7.6mm>
上記の数値目指して、手順⑤ サドルを削ります!
削る時に使うものは、100番・180番・240番のサンドペーパー。そして、しっかり平らな面を出す為に、強化ガラスを台に使用しました。

で、あとは、手の感覚に全てをゆだね、ゆっくりとサドル底面を削っていきます。

始めは180番のサンドペーパーで削っていましたが、サドルって結構硬いんです。全然削れていかないので、最初の『慎重に丁寧に』の合言葉も忘れ、100番でガシガシと削りました。
ただ、時々、サドルの底面をガラスに当ててみて『均等に削れているかを確認』します。問題の底面の角度については、本当に手の感覚が頼りでしたが、何とか上手くいきそうです。自分の手は工業用ロボットだと言い聞かせ、削る前の角度を変えないように固定し、注意しながら削った訳です。
で、『ある程度削ったら測定』を繰り返しました。
この一連の、『均等に削れているかの確認』と『ある程度削ったら測定』は、面倒に思わずにマメにやった方が良いと思います。それと、もしサドルの底面が斜めではなく平らだったら、サンドペーパーに『直角』に当てることと、『直角をキープできているかの確認』も怠ってはいけません。まぁ、今回はこの確認が必要ありませんでしたが・・・。
さぁ、とうとうサドルの厚さが目標の数値に近付きました。ここからは、サンドペーパーを180番に変えます。微調整ですね。シャカシャカシャカ・・・
で、とうとう、目標の数値に到達。時間にして15分ぐらいでしたので、思ったほど時間は掛かりませんでした。
削った後のサドルの測定です。
1弦側<5.7mm> 6弦側<7.5mm>
あれ?1弦側は目標にピッタリですが、6弦側は<0.1mm>削り過ぎですね・・・。
まぁ、この程度なら大丈夫だと思いますので・・・続行いたします。
手順⑦ サドルをギターにセットし弦を張ってチューニングしたあと弦高を測ります。
この時、弦はギターのペグの部分に巻いたままになっていますので、それほど手間を掛けずに弦を張ることができます。で、チューニングしました。
弦高を測定してみます。ドキドキ・・・
出ました!
1弦

シックネスゲージの<1.0mm>と<0.7mm>の組み合わせでピッタリ!
という事は、目標の<1.7mm>丁度です!
6弦

ゲージの<1.0mm>と<0.9mm>と<0.5mm>の組み合わせでピッタリ!ということは・・えっと・・・
<2.4mm>で、目標よりもやはり<0.1mm>低くなりました。まぁ、問題ないでしょう。
という訳で、一回で目標の弦高を(だいたい)達成できました!
もしこの時点で弦高が目標の数値に到達していなかったら、もう一度ギターからサドルを外して、削って、戻して、弦を張って・・・とやらなければなりません。
最初の①②での測定と計算。そして、⑤⑥のサドルを削りながらマメにチェック。この手順がとても大切だということですね。
さて、これで一応、私の初めての弦高調整が終わりました。
サドルの底面が斜めだと分かった時には、ちょっとビビリましたが。結果的には、その斜めの角度をほぼ正確に保ったまま削れたと思います。私の手の感覚もなかなか。
今回の弦高調整に掛かった時間は、合計で1時間30分ぐらいだと思います。
やる前は、とても気を使う大変な作業かと思っていましたが、ある程度の器具を準備して、測定の部分で手を抜かずにしっかりやれば、意外と簡単な作業でした。
そして、大事な弾き心地ですけど・・・続く。
☆記事に登場した機材をAmazonで見る!
豊光 26枚シックネスゲージ ビニールポーチ入リ M240M


シンワ測定 高級ミニノギス 100mm


☆関連記事
・ヤマハ エレアコギター APX700II
・ヤマハ エレアコギター APX700II の弦高調整
・ヤマハ エレアコギター APX700II の弦高調整2
・ヤマハ エレアコギター APX700II の弦高調整後の弾き心地
・ヤマハ エレアコギター APX700IIにコンデンサーマイクCM-1を付ける!
・ピエゾ+コンデンサーマイクCM-1の音の検証
☆厳選!ギターを始めたばかりの方にお勧めの記事3つ!
厳選1 メロディ演奏にもコード伴奏にも密接な関連があるCメジャースケール。ギターを初めて触った時から上級者になるまでの練習の必須項目!
【Cメジャースケールを練習しよう!~ギターにおけるCメジャースケールの重要性~】
厳選2 ギターで最初に練習するべき曲は教則本には載っていない場合が多いんです!最初にどんな曲を弾くべきか?またその判別方法は?
【ギターで最初に挑戦する曲は?~キィの判別と教則本の落とし穴~】
厳選3 sinyaが猛烈プッシュするギターの新しい練習方法!いずれは、この練習がギターリストにとっての当たり前になると本気で思っています。ギターの全てが詰まった画期的な練習です!
【ギターリストの新しい練習方法~二胡譜の活用~】


【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!
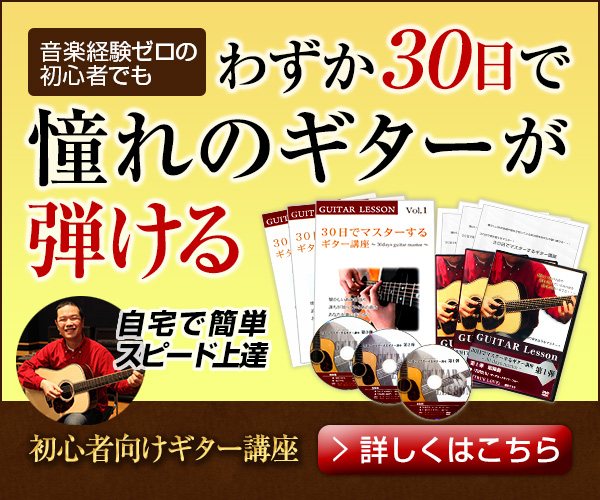

APX700から外したサドルの底面が、斜めだった件。写真では分かり難かったので、図で説明します。
従来のサドルは、底面が平らです。なので、底面を削る時には、サドルをサンドペーパーに『直角』に当てます。削っている最中にも、時々その『直角』を確認することによって、底面が平らに削られているかどうかの判断をする訳です。
ところが、APX700は図の右のように、サドルの底面が斜めになっていました。これでは、サンドペーパーに『直角』に当てることは出来ません。『直角』に当てることが出来ないということは、平らに削られているかどうかの判断材料を失ってしまうことになります。
とはいえ、いてもたっていられずに始めた作業なので、ここで止めるのも悔しいし、今から新しいサドルを注文して届くまで待てる自信もありません。
で、考えられる案は2つ。
第一案・・・斜めになっている部分を削って平らにしてしまう。
第二案・・・斜めのまま削る。
APX700のサドルの底面が、なぜ斜めになっているのか?その理由は分かりません。ただ、もちろん意味があってのことだと思います。なので、出来れば斜めの状態を保ちたい。
そして、第一案のように斜めの部分をカットしてしまうと、予定の削る量を大幅にオーバーしてしまいます。サドルの底を削る量は、前回の計算では<0.4mm>です。斜めの部分をカットしたら、恐らくその倍は削れてしまいます。
そんなに削ったら、弦高が低くなり過ぎて、音に支障が出てしまうと思います。
という訳で、第二案を決行いたします。
『直角』があてにならない以上、削る前の斜めの角度を保ちながら削る他ありません。
しかし、斜めの角度を正確に保ちながら底面を削る方法が思い浮かばないので、全てを『自分の手の感覚』にゆだねることにしました。
う~ん、職人さんみたいでカッコイイです。もう一度言います、私、アコギの弦高調整は初めてです。
そうと決まりましたので。作業を続行いたします。
前回、手順③までいきましたので、手順④ 削る前のサドルを測定します。
サドルは、真っ白い部品です。そのままでは、どこを基点に測定して良いのか分かりません。なので、計測の基点となる線をマジックで入れます。これは、1弦と6弦の当たる位置の2箇所で良いと思います。が、何となく1弦~6弦の全6箇所に印を付けてしまいました。

この計測基点を元に測ります。

測定の結果、削る前のサドルは以下のような状態でした。
削る前のサドルの寸法
1弦側<6.1mm> 6弦側<8.0mm>
ちなみに測定には『ノギス』を使います。

本尺目盛りと副尺目盛りを組み合わせることにより、最小で<0.05mm>まで読み取ることが出来ます。サドルを削る量は<0.4mm>と、1mm以下を正確に測る必要がありますので。やはり、ノギスを使った方が良いですね。
削る量が<0.4mm>なので、サドルの目標数値は以下のようになります。
1弦側 6.1-0.4 = <5.7mm>
6弦側 8.0-0.4 = <7.6mm>
上記の数値目指して、手順⑤ サドルを削ります!
削る時に使うものは、100番・180番・240番のサンドペーパー。そして、しっかり平らな面を出す為に、強化ガラスを台に使用しました。

で、あとは、手の感覚に全てをゆだね、ゆっくりとサドル底面を削っていきます。

始めは180番のサンドペーパーで削っていましたが、サドルって結構硬いんです。全然削れていかないので、最初の『慎重に丁寧に』の合言葉も忘れ、100番でガシガシと削りました。
ただ、時々、サドルの底面をガラスに当ててみて『均等に削れているかを確認』します。問題の底面の角度については、本当に手の感覚が頼りでしたが、何とか上手くいきそうです。自分の手は工業用ロボットだと言い聞かせ、削る前の角度を変えないように固定し、注意しながら削った訳です。
で、『ある程度削ったら測定』を繰り返しました。
この一連の、『均等に削れているかの確認』と『ある程度削ったら測定』は、面倒に思わずにマメにやった方が良いと思います。それと、もしサドルの底面が斜めではなく平らだったら、サンドペーパーに『直角』に当てることと、『直角をキープできているかの確認』も怠ってはいけません。まぁ、今回はこの確認が必要ありませんでしたが・・・。
さぁ、とうとうサドルの厚さが目標の数値に近付きました。ここからは、サンドペーパーを180番に変えます。微調整ですね。シャカシャカシャカ・・・
で、とうとう、目標の数値に到達。時間にして15分ぐらいでしたので、思ったほど時間は掛かりませんでした。
削った後のサドルの測定です。
1弦側<5.7mm> 6弦側<7.5mm>
あれ?1弦側は目標にピッタリですが、6弦側は<0.1mm>削り過ぎですね・・・。
まぁ、この程度なら大丈夫だと思いますので・・・続行いたします。
手順⑦ サドルをギターにセットし弦を張ってチューニングしたあと弦高を測ります。
この時、弦はギターのペグの部分に巻いたままになっていますので、それほど手間を掛けずに弦を張ることができます。で、チューニングしました。
弦高を測定してみます。ドキドキ・・・
出ました!
1弦

シックネスゲージの<1.0mm>と<0.7mm>の組み合わせでピッタリ!
という事は、目標の<1.7mm>丁度です!
6弦

ゲージの<1.0mm>と<0.9mm>と<0.5mm>の組み合わせでピッタリ!ということは・・えっと・・・
<2.4mm>で、目標よりもやはり<0.1mm>低くなりました。まぁ、問題ないでしょう。
という訳で、一回で目標の弦高を(だいたい)達成できました!
もしこの時点で弦高が目標の数値に到達していなかったら、もう一度ギターからサドルを外して、削って、戻して、弦を張って・・・とやらなければなりません。
最初の①②での測定と計算。そして、⑤⑥のサドルを削りながらマメにチェック。この手順がとても大切だということですね。
さて、これで一応、私の初めての弦高調整が終わりました。
サドルの底面が斜めだと分かった時には、ちょっとビビリましたが。結果的には、その斜めの角度をほぼ正確に保ったまま削れたと思います。私の手の感覚もなかなか。
今回の弦高調整に掛かった時間は、合計で1時間30分ぐらいだと思います。
やる前は、とても気を使う大変な作業かと思っていましたが、ある程度の器具を準備して、測定の部分で手を抜かずにしっかりやれば、意外と簡単な作業でした。
そして、大事な弾き心地ですけど・・・続く。
☆記事に登場した機材をAmazonで見る!
豊光 26枚シックネスゲージ ビニールポーチ入リ M240M

シンワ測定 高級ミニノギス 100mm

☆関連記事
・ヤマハ エレアコギター APX700II
・ヤマハ エレアコギター APX700II の弦高調整
・ヤマハ エレアコギター APX700II の弦高調整2
・ヤマハ エレアコギター APX700II の弦高調整後の弾き心地
・ヤマハ エレアコギター APX700IIにコンデンサーマイクCM-1を付ける!
・ピエゾ+コンデンサーマイクCM-1の音の検証
☆厳選!ギターを始めたばかりの方にお勧めの記事3つ!
厳選1 メロディ演奏にもコード伴奏にも密接な関連があるCメジャースケール。ギターを初めて触った時から上級者になるまでの練習の必須項目!
【Cメジャースケールを練習しよう!~ギターにおけるCメジャースケールの重要性~】
厳選2 ギターで最初に練習するべき曲は教則本には載っていない場合が多いんです!最初にどんな曲を弾くべきか?またその判別方法は?
【ギターで最初に挑戦する曲は?~キィの判別と教則本の落とし穴~】
厳選3 sinyaが猛烈プッシュするギターの新しい練習方法!いずれは、この練習がギターリストにとっての当たり前になると本気で思っています。ギターの全てが詰まった画期的な練習です!
【ギターリストの新しい練習方法~二胡譜の活用~】


【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!
Posted by sinya at 16:55
│調整・メンテナンス