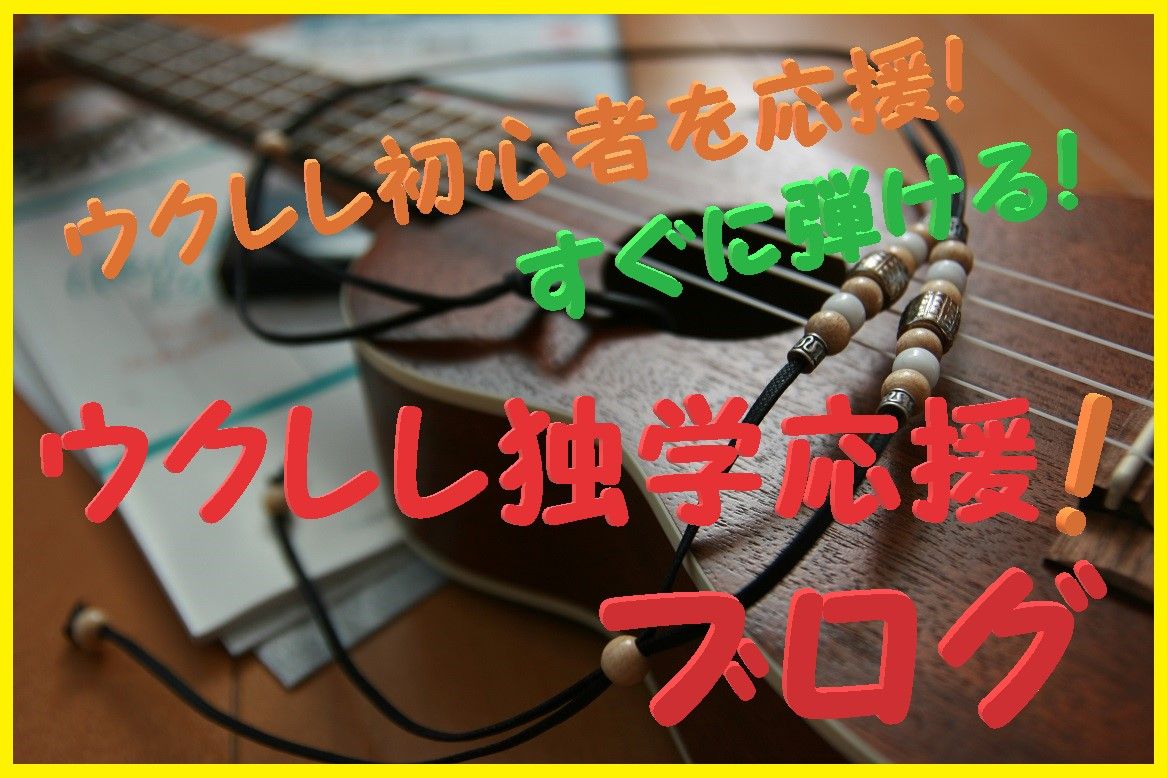2013年01月10日
アコギに使えるピックアップの種類
⇒【sinyaが開発!弾く脳トレ!よなおしギター】
昨日の記事【ギターの音で最も大切な要素】では、ギターの音量に関連したお話です。
アコースティックギターは、マイクを通さない音(生音)がまず基本となります。ですから、昨日の『大きな音から小さな音まで自在に操る』というのは、ギターの生音での音量のお話で。それは例えば、ボーカリストが自分のお腹と喉を駆使して音量を調節するのと似ています。
ボーカリストもスタジオ練習やライブになれば当然、マイクを使いますが、その場合のマイクは『人間から出た音を大きくする』ことが基本の働きとなりますね。
アコースティックギターにマイクを使う場合も同じようなことが言えます。
まず自分の腕・テクニックを使って生音でしっかりと音量調節をすることが大前提となります。その上で、レコーディングの時やバンドなどで他の楽器とセッションをする時にマイクを使うことになります。
やはりその場合も、マイクの役目は『ギターそのものの音を大きくする』ことが基本となるんです。
ここが、音色をイロイロ変化させることを前提にマイク(ピックアップ)を使うエレキギターとの大きな違いです。
さて、アコースティックギターでマイクを使用する場合でも、特に良い音を追求する必要のあるレコーディングでは、ボーカルのレコーディングと同じように、ギターの前にコンデンサーマイクを設置して録音することが多いと思います。(テレビなどでボーカリストがレコーディングする映像が流れることがありますが、その時にボーカリストの前に吊るされたり立てられたりしている大き目のマイクがコンデンサーマイクです。)
この場合、エンジニアによって、ギターとマイクの位置・角度が最上の音を録音する為に徹底的に追求され。そのギターとマイクの位置関係が演奏中に崩れないように、ギターを固定させることも少なくないと思います。
ただ、ライブなどではそうもいきませんね。
ライブは演奏も大事ですが、それ以上に演奏も含めた総合的なパフォーマンスが最も大切になりますから。
少しでも動いたらバランスが崩れてしまうシビアなギターとマイクのセッティングは、不可能に近い訳です。
そこで誕生するのが、マイク(ピックアップ)がギター本体に内蔵されたエレクトリックアコースティックギター略してエレアコです。
ギターを製造する過程で、良い音が出る位置にマイクを付けてしまえば、ライブでどんなに活発に動いても音質は変わらず安定させることが出来る訳です。
そんなエレアコには、主に3種類のピックアップが使われます。簡単にまとめてみます。
①ピエゾタイプ
エレアコのピックアップでは最もポピュラーなマイクです。薄いシールのような形状で、ギターの表板の裏に1~複数個のピエゾピックアップを付けます。付ける場所によって音色が変わるので、付ける作業は簡単ですが、良い音を出す為には研究が必要です。
音は、高音が強調された『シャキシャキ』した独特の音がします。
②コンデンサータイプ
ボーカリストの録音などに使われるコンデンサーマイクをギューっと小さくしてギターの中に仕込みます。このタイプのマイクは、空気の振動を拾いますので、人間が普段聞いている音に最も近い音が出ることになります。ギターそのものの音を出すには最も適したマイクで比較的セッティングも簡単ですが、ハウリングしやすいという欠点があります。
音は、『空気感』があり人間の耳に馴染みやすい音だと思います。どちらかというと『モワッ』とした低中音が強調された音になります。
③マグネットタイプ
エレキギターのピックアップと同じ構造です。名前からも分かる通り、エレキのような鉄製の弦に有効なピックアップです。取り付けが非常に簡単で、ほとんどの場合、ギターとは別に購入して自分で後から付けることになります。取り付ける場所は、ギターのサウンドホール(真ん中の穴です)がほとんどです。
音に関しては、正直、私はこのタイプのピックアップを使ったことが無いのですが、調べると、良くも悪くもエレキの音に近いようです。低音はよく出るようですが、特に高音弦がエレキっぽいようです。
いずれのピックアップも、ギターに内蔵することを前提に作られていますので、大きさに制約があるためでしょう『これ1つで完璧!』というものはありません。
また、エレキのようにエフェクターで思いっきり音色を変えることがないので、いわば『誤魔化し』が効きません。なので、エレアコを作るメーカーはもちろん、演奏する方も、何とかライブで『ギター本来の音』を出す為に日夜研究に研究を重ねている訳です。
それでも、やはりそれぞれに欠点があるピックアップ、今の時点で『これ1つで完璧!』というピックアップがないのは仕方のないことでしょう。ただ、それを解決する方法があります。
それが『ピックアップの組み合わせ』です。
それぞれの欠点を補って、さらにそれぞれの良いところを出し合うことで、より理想に近い音を出そうという訳です。
ピックアップの組み合わせは、①~③の3つ全部を組み合わせることはほとんどありません。が、2種類の組み合わせなら、どの組み合わせもやってみる価値はあると思います。
自分の好みや演奏スタイル、ギターとの相性など、イロイロ考えてピックアップの組み合わせを考えてみるのも非常に楽しい作業だと思います。
と言う訳で。私も数年前から、アコースティックギターにピックアップを付けるのなら2種類を組み合わせて使おうと思っていました。
何と何を組み合わせようかとズ~っと楽しく悩んでいましたが。この度、とても良いピックアップを見つけた事により、組み合わせ方が決まったんです。
そのピックアップのご紹介と組み合わせの説明は、長くなりますので、次回以降とさせて頂きます。
☆関連記事
・ギターの音で最も大切な要素
・アコギに使えるピックアップの種類
・BOSS AD5
・コムミュージック CM-1
・ヤマハ エレアコギター APX700II BL
・ヤマハ エレアコギター APX700IIにコンデンサーマイクCM-1を付ける!
・ピエゾ+コンデンサーマイクCM-1の音の検証


【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!
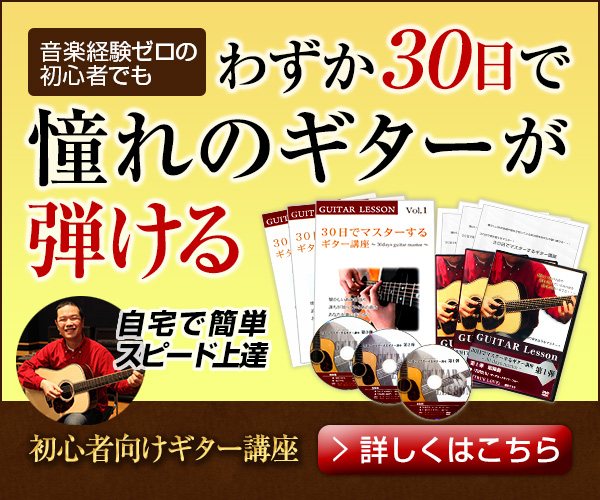

昨日の記事【ギターの音で最も大切な要素】では、ギターの音量に関連したお話です。
アコースティックギターは、マイクを通さない音(生音)がまず基本となります。ですから、昨日の『大きな音から小さな音まで自在に操る』というのは、ギターの生音での音量のお話で。それは例えば、ボーカリストが自分のお腹と喉を駆使して音量を調節するのと似ています。
ボーカリストもスタジオ練習やライブになれば当然、マイクを使いますが、その場合のマイクは『人間から出た音を大きくする』ことが基本の働きとなりますね。
アコースティックギターにマイクを使う場合も同じようなことが言えます。
まず自分の腕・テクニックを使って生音でしっかりと音量調節をすることが大前提となります。その上で、レコーディングの時やバンドなどで他の楽器とセッションをする時にマイクを使うことになります。
やはりその場合も、マイクの役目は『ギターそのものの音を大きくする』ことが基本となるんです。
ここが、音色をイロイロ変化させることを前提にマイク(ピックアップ)を使うエレキギターとの大きな違いです。
さて、アコースティックギターでマイクを使用する場合でも、特に良い音を追求する必要のあるレコーディングでは、ボーカルのレコーディングと同じように、ギターの前にコンデンサーマイクを設置して録音することが多いと思います。(テレビなどでボーカリストがレコーディングする映像が流れることがありますが、その時にボーカリストの前に吊るされたり立てられたりしている大き目のマイクがコンデンサーマイクです。)
この場合、エンジニアによって、ギターとマイクの位置・角度が最上の音を録音する為に徹底的に追求され。そのギターとマイクの位置関係が演奏中に崩れないように、ギターを固定させることも少なくないと思います。
ただ、ライブなどではそうもいきませんね。
ライブは演奏も大事ですが、それ以上に演奏も含めた総合的なパフォーマンスが最も大切になりますから。
少しでも動いたらバランスが崩れてしまうシビアなギターとマイクのセッティングは、不可能に近い訳です。
そこで誕生するのが、マイク(ピックアップ)がギター本体に内蔵されたエレクトリックアコースティックギター略してエレアコです。
ギターを製造する過程で、良い音が出る位置にマイクを付けてしまえば、ライブでどんなに活発に動いても音質は変わらず安定させることが出来る訳です。
そんなエレアコには、主に3種類のピックアップが使われます。簡単にまとめてみます。
①ピエゾタイプ
エレアコのピックアップでは最もポピュラーなマイクです。薄いシールのような形状で、ギターの表板の裏に1~複数個のピエゾピックアップを付けます。付ける場所によって音色が変わるので、付ける作業は簡単ですが、良い音を出す為には研究が必要です。
音は、高音が強調された『シャキシャキ』した独特の音がします。
②コンデンサータイプ
ボーカリストの録音などに使われるコンデンサーマイクをギューっと小さくしてギターの中に仕込みます。このタイプのマイクは、空気の振動を拾いますので、人間が普段聞いている音に最も近い音が出ることになります。ギターそのものの音を出すには最も適したマイクで比較的セッティングも簡単ですが、ハウリングしやすいという欠点があります。
音は、『空気感』があり人間の耳に馴染みやすい音だと思います。どちらかというと『モワッ』とした低中音が強調された音になります。
③マグネットタイプ
エレキギターのピックアップと同じ構造です。名前からも分かる通り、エレキのような鉄製の弦に有効なピックアップです。取り付けが非常に簡単で、ほとんどの場合、ギターとは別に購入して自分で後から付けることになります。取り付ける場所は、ギターのサウンドホール(真ん中の穴です)がほとんどです。
音に関しては、正直、私はこのタイプのピックアップを使ったことが無いのですが、調べると、良くも悪くもエレキの音に近いようです。低音はよく出るようですが、特に高音弦がエレキっぽいようです。
いずれのピックアップも、ギターに内蔵することを前提に作られていますので、大きさに制約があるためでしょう『これ1つで完璧!』というものはありません。
また、エレキのようにエフェクターで思いっきり音色を変えることがないので、いわば『誤魔化し』が効きません。なので、エレアコを作るメーカーはもちろん、演奏する方も、何とかライブで『ギター本来の音』を出す為に日夜研究に研究を重ねている訳です。
それでも、やはりそれぞれに欠点があるピックアップ、今の時点で『これ1つで完璧!』というピックアップがないのは仕方のないことでしょう。ただ、それを解決する方法があります。
それが『ピックアップの組み合わせ』です。
それぞれの欠点を補って、さらにそれぞれの良いところを出し合うことで、より理想に近い音を出そうという訳です。
ピックアップの組み合わせは、①~③の3つ全部を組み合わせることはほとんどありません。が、2種類の組み合わせなら、どの組み合わせもやってみる価値はあると思います。
自分の好みや演奏スタイル、ギターとの相性など、イロイロ考えてピックアップの組み合わせを考えてみるのも非常に楽しい作業だと思います。
と言う訳で。私も数年前から、アコースティックギターにピックアップを付けるのなら2種類を組み合わせて使おうと思っていました。
何と何を組み合わせようかとズ~っと楽しく悩んでいましたが。この度、とても良いピックアップを見つけた事により、組み合わせ方が決まったんです。
そのピックアップのご紹介と組み合わせの説明は、長くなりますので、次回以降とさせて頂きます。
☆関連記事
・ギターの音で最も大切な要素
・アコギに使えるピックアップの種類
・BOSS AD5
・コムミュージック CM-1
・ヤマハ エレアコギター APX700II BL
・ヤマハ エレアコギター APX700IIにコンデンサーマイクCM-1を付ける!
・ピエゾ+コンデンサーマイクCM-1の音の検証


【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!
Posted by sinya at 21:30
│機材