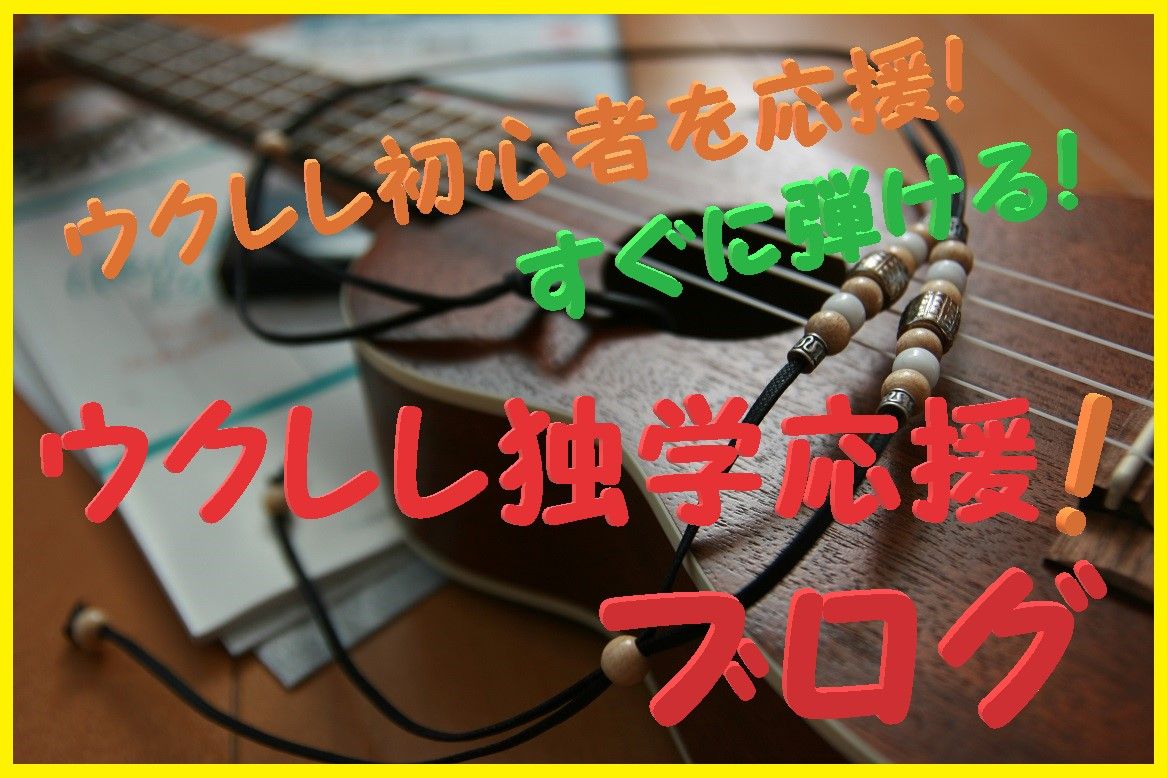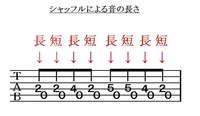2013年06月12日
フラットピックを使ったコードストロークのコツ
⇒【sinyaが開発!弾く脳トレ!よなおしギター】
昨日の記事【ピックを使わずに練習することの必要性】の続きになります。
アコースティックギターを練習する時に、もし『ピックを使わずに練習』していると、その内にピックを使わないことに『限界』を感じてくることを、昨日の記事でお話ししました。
その『限界』は、ほとんどの場合『音量』にあります。
自宅で独りギターを弾いている時には、それほど音量に関して物足りなさを感じないものですが。教室にて、二人でセッションなどをする時には、やはりある程度の音量が必要になってきます。
そんな場合、アコギの弦は硬い訳ですから、そんな弦を素手で弾くと、音量が物足りなくなると同時に、指も痛くなり『限界』を感じることになります。
ただ、その段階では、セッションが出来るほど技術的にも上達していて、しかも、『音量の大切さ』を自然に感じた訳ですから。もう、ピックを使ったとしても、他の演奏者の音も聴かずにやたらガシガシと大きな音で弾いてしまうようなことも無い訳です。
素晴らしいですね!
ただそれでも、そこまで上達した方でも習得するのが難しいピッキングの技術は、やはりあります。
その1つが、フラットピックを使った『思い切ったコードストローク』です。
『思い切ったコードストローク』が難しい理由の1つに、コードチェンジを素早くスムーズに行わないと音がしっかり鳴らないということがあります。
が、それよりも肝心なのが『右手の動き』になると思います。
私がギターを始めた頃は、アコギ(当時はフォークギターと言っていました)のコードストロークの説明として『右手の肘を軸にして上下に動かすこと』と、多分、どの教則本にも書いてあったと思います。その時『右手の手首は動かさずに肘からピックを持つ指までを真っ直ぐな状態に保つ』ようになっていました。
あの頃は、フォークギターといえば『弾き語りの伴奏楽器』という位置付けが主でしたので。大きなボディに太い弦を張って、歌いながら『ガッシャガシャ』と掻き鳴らすイメージでしたね。
ですから、コードストロークも、ある意味『力ずく』で、手首をガチッと硬くして弾くような風潮だったように思います。
でも今現在、ギターを取り巻く環境は、全く変わりましたね。
さまざまな奏法が日本でも研究・確立され、それに合わせて、さまざまなタイプのギターが一般の人たちにも簡単に手に入るようになりました。
ギターのサイズは小さくなる傾向に、弦は細く、弦高は低く。音量やパワーだけではなく、弾き易さや繊細さも求められるようになりました。
もう、昔のような『掻き鳴らすストローク』だけでは対応できなくなったんですね。
では、今のアコースティックギターの演奏においては、どんな『コードストローク』が理想的なのでしょうか?
私なりに考えてみます。
先ほども言いましたように、今の時代に求められる『ストローク』は、さまざまなギターで、さまざまな楽曲に対応できなければなりません。その為には、右手の『3箇所の動き』を制御する必要があると思います。
1.右手の肘の動き
2.右手の手首の動き
3.右手の親指の動き
以上の3箇所を、さまざまなシチュエーションに合わせて、微妙にシンクロさせて動かしていくことになります。
実は、この3つの動きをシンクロさせる方法は、『繊細で複雑なピッキング』が常に要求されるエレキギターのピッキングの方法と同じなんです。
エレキギターの場合、もちろんコードストロークもありますが、メロディやベースラインの演奏からミュート技術やアルペジオまで、ほとんどの場合フラットピック1枚で行うのですから。とても『繊細で複雑なピッキング』になる訳です。
今のアコギが、小型化し、弦が細く、弦高が低くなってきたということは、ある意味『アコギがエレキギターの弾き心地に近付いた』といえると思います。
そうなれば当然、ピッキングに関しても、エレキギターのピッキングに近付ける必要がある訳ですね。
で、上記の3つの動きが大切といことになるのですが。
その中でも、私が最も大切だと思うのが『2.手首の動き』です。
そして、この一番大切な『手首の動き』が、特に『ピックを使わずに練習』してきたアコースティック・ギターリストには、なかなか難しい技術となってきます。
今まで私は、この『手首の動き』、特にストローク(カッティングも含む)のコツを教室で説明する時に「体温計を振る時のように右手を動かして下さい」とお伝えしていました。
ただ、その解説に、若い方たちは『ポッカーン』となるんです。当然ですね。今時の体温計は『ピピッ』っとやれば一瞬でリセットされて、直ぐに体温を測ることが出来る訳ですから。
体温計を振る必要なんて、一切ありません。
なので、最近では、『手首の動き』のコツとして、以下のようにお伝えすることにしています。
『カップラーメンなどに付いている粉末スープの袋を開ける前に、袋を右手で持って振る動き』をイメージしてください!
多分、皆さん、粉末スープの袋を開ける前に、粉末を袋の下の方に集める為に、右手に袋を持って『振り』ますよね?
あの動きって、袋を持つ指先の形から、手首の角度と動き、腕の回転など、全てにおいて『理想的なピッキングの動き』に酷似しているんです。
興味のある方は、試してみてください。
二回に渡ってピッキングのことについて長々と書いてきたのに、最終的な結論が『カップラーメンの粉末スープ・・・』って・・・
でも、結構真面目に書きましたので、ご了承下さい。
☆厳選!ギターを始めたばかりの方にお勧めの記事3つ!
厳選1 メロディ演奏にもコード伴奏にも密接な関連があるCメジャースケール。ギターを初めて触った時から上級者になるまでの練習の必須項目!
【Cメジャースケールを練習しよう!~ギターにおけるCメジャースケールの重要性~】
厳選2 ギターで最初に練習するべき曲は教則本には載っていない場合が多いんです!最初にどんな曲を弾くべきか?またその判別方法は?
【ギターで最初に挑戦する曲は?~キィの判別と教則本の落とし穴~】
厳選3 sinyaが猛烈プッシュするギターの新しい練習方法!いずれは、この練習がギターリストにとっての当たり前になると本気で思っています。ギターの全てが詰まった画期的な練習です!
【ギターリストの新しい練習方法~二胡譜の活用~】


【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!
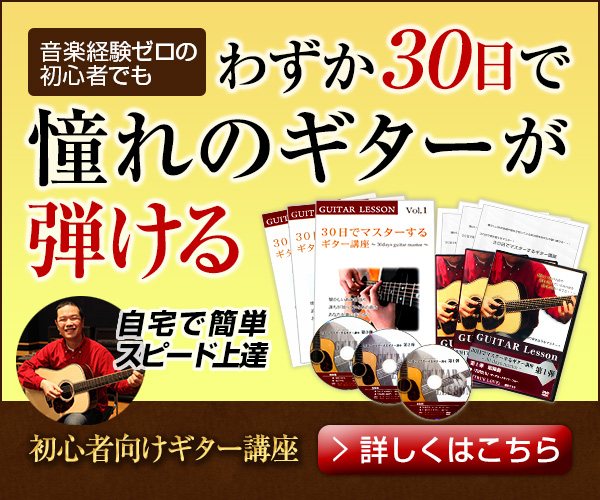

昨日の記事【ピックを使わずに練習することの必要性】の続きになります。
アコースティックギターを練習する時に、もし『ピックを使わずに練習』していると、その内にピックを使わないことに『限界』を感じてくることを、昨日の記事でお話ししました。
その『限界』は、ほとんどの場合『音量』にあります。
自宅で独りギターを弾いている時には、それほど音量に関して物足りなさを感じないものですが。教室にて、二人でセッションなどをする時には、やはりある程度の音量が必要になってきます。
そんな場合、アコギの弦は硬い訳ですから、そんな弦を素手で弾くと、音量が物足りなくなると同時に、指も痛くなり『限界』を感じることになります。
ただ、その段階では、セッションが出来るほど技術的にも上達していて、しかも、『音量の大切さ』を自然に感じた訳ですから。もう、ピックを使ったとしても、他の演奏者の音も聴かずにやたらガシガシと大きな音で弾いてしまうようなことも無い訳です。
素晴らしいですね!
ただそれでも、そこまで上達した方でも習得するのが難しいピッキングの技術は、やはりあります。
その1つが、フラットピックを使った『思い切ったコードストローク』です。
『思い切ったコードストローク』が難しい理由の1つに、コードチェンジを素早くスムーズに行わないと音がしっかり鳴らないということがあります。
が、それよりも肝心なのが『右手の動き』になると思います。
私がギターを始めた頃は、アコギ(当時はフォークギターと言っていました)のコードストロークの説明として『右手の肘を軸にして上下に動かすこと』と、多分、どの教則本にも書いてあったと思います。その時『右手の手首は動かさずに肘からピックを持つ指までを真っ直ぐな状態に保つ』ようになっていました。
あの頃は、フォークギターといえば『弾き語りの伴奏楽器』という位置付けが主でしたので。大きなボディに太い弦を張って、歌いながら『ガッシャガシャ』と掻き鳴らすイメージでしたね。
ですから、コードストロークも、ある意味『力ずく』で、手首をガチッと硬くして弾くような風潮だったように思います。
でも今現在、ギターを取り巻く環境は、全く変わりましたね。
さまざまな奏法が日本でも研究・確立され、それに合わせて、さまざまなタイプのギターが一般の人たちにも簡単に手に入るようになりました。
ギターのサイズは小さくなる傾向に、弦は細く、弦高は低く。音量やパワーだけではなく、弾き易さや繊細さも求められるようになりました。
もう、昔のような『掻き鳴らすストローク』だけでは対応できなくなったんですね。
では、今のアコースティックギターの演奏においては、どんな『コードストローク』が理想的なのでしょうか?
私なりに考えてみます。
先ほども言いましたように、今の時代に求められる『ストローク』は、さまざまなギターで、さまざまな楽曲に対応できなければなりません。その為には、右手の『3箇所の動き』を制御する必要があると思います。
1.右手の肘の動き
2.右手の手首の動き
3.右手の親指の動き
以上の3箇所を、さまざまなシチュエーションに合わせて、微妙にシンクロさせて動かしていくことになります。
実は、この3つの動きをシンクロさせる方法は、『繊細で複雑なピッキング』が常に要求されるエレキギターのピッキングの方法と同じなんです。
エレキギターの場合、もちろんコードストロークもありますが、メロディやベースラインの演奏からミュート技術やアルペジオまで、ほとんどの場合フラットピック1枚で行うのですから。とても『繊細で複雑なピッキング』になる訳です。
今のアコギが、小型化し、弦が細く、弦高が低くなってきたということは、ある意味『アコギがエレキギターの弾き心地に近付いた』といえると思います。
そうなれば当然、ピッキングに関しても、エレキギターのピッキングに近付ける必要がある訳ですね。
で、上記の3つの動きが大切といことになるのですが。
その中でも、私が最も大切だと思うのが『2.手首の動き』です。
そして、この一番大切な『手首の動き』が、特に『ピックを使わずに練習』してきたアコースティック・ギターリストには、なかなか難しい技術となってきます。
今まで私は、この『手首の動き』、特にストローク(カッティングも含む)のコツを教室で説明する時に「体温計を振る時のように右手を動かして下さい」とお伝えしていました。
ただ、その解説に、若い方たちは『ポッカーン』となるんです。当然ですね。今時の体温計は『ピピッ』っとやれば一瞬でリセットされて、直ぐに体温を測ることが出来る訳ですから。
体温計を振る必要なんて、一切ありません。
なので、最近では、『手首の動き』のコツとして、以下のようにお伝えすることにしています。
『カップラーメンなどに付いている粉末スープの袋を開ける前に、袋を右手で持って振る動き』をイメージしてください!
多分、皆さん、粉末スープの袋を開ける前に、粉末を袋の下の方に集める為に、右手に袋を持って『振り』ますよね?
あの動きって、袋を持つ指先の形から、手首の角度と動き、腕の回転など、全てにおいて『理想的なピッキングの動き』に酷似しているんです。
興味のある方は、試してみてください。
二回に渡ってピッキングのことについて長々と書いてきたのに、最終的な結論が『カップラーメンの粉末スープ・・・』って・・・
でも、結構真面目に書きましたので、ご了承下さい。
☆厳選!ギターを始めたばかりの方にお勧めの記事3つ!
厳選1 メロディ演奏にもコード伴奏にも密接な関連があるCメジャースケール。ギターを初めて触った時から上級者になるまでの練習の必須項目!
【Cメジャースケールを練習しよう!~ギターにおけるCメジャースケールの重要性~】
厳選2 ギターで最初に練習するべき曲は教則本には載っていない場合が多いんです!最初にどんな曲を弾くべきか?またその判別方法は?
【ギターで最初に挑戦する曲は?~キィの判別と教則本の落とし穴~】
厳選3 sinyaが猛烈プッシュするギターの新しい練習方法!いずれは、この練習がギターリストにとっての当たり前になると本気で思っています。ギターの全てが詰まった画期的な練習です!
【ギターリストの新しい練習方法~二胡譜の活用~】


【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!
Posted by sinya at 23:41
│ギター教室